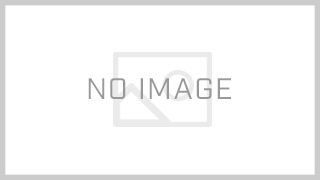- ✨ 失敗しないための設計・検討ガイドライン
- 📘 マニュアル目次
- 🔌 1. 高圧受電設備の結線図と使用機器
- 🛠️ 2. 設計手順(検討項目と要点)
- 💡 3. 電力需給用計器用変成器(VCT)、電力量計(Wh)
- 🛡️ 4. 断路器(DS: Disconnecting Switches / 89R)
- 🏗️ 5. 主遮断装置の形式、受電設備方式、設備容量
- ⚡ 6. CB形受電設備(Circuit Breaker)
- ⚡CB形受電設備の構成と選定ポイント
- 💡 7. PF・S形受電設備(Power Fuse & Switch)
- 📈 8. 計器・計測器
- 🛡️ 9. 保護装置
- 10. 監視・制御装置
- 💡 11. 変成器(VT)、変流器(CT)、零相変流器(ZCT)
- 🔎 解説ポイント
- ✅ 実務上の注意点
- 🌎 12. 接地工事(安全確保の基本)
- 📏 13. キュービクルの配置と保有距離
- 🔥 14. 認定キュービクル、推奨キュービクル
✨ 失敗しないための設計・検討ガイドライン
設計実務者が迷わず、迅速に、そして安全に設計を進めるために必要な手順と要点を、よりわかりやすい解説形式でまとめました。
📘 マニュアル目次
| 項目名 | 概要 |
| 高圧受電設備の結線図と使用機器 | 設計図面で使用される主要機器の略称と構成要素の役割 |
| 設計手順(検討項目と要点) | 短絡電流に基づく機器・電線選定の基準と具体的なステップ |
| 電力需給用計器用変成器、電力量計 | 設置場所の決定(電力会社別)と設計上の留意点 |
| 断路器 | 選定要件、機能、規格、インターロックの要点 |
| 主遮断装置の形式、受電設備方式、設備容量 | 設備容量の制限、受電形式の定義、施設場所の検討 |
| CB形受電設備 | 遮断器(CB/VCB)の種類、規格、選定要件、DSとの関係、操作・引外し方式 |
| PF・S形受電設備 | 選定要件、容量制限、 の種類、ヒューズ選定例 |
| 計器・計測器 | 標準/オプション計器、電子式マルチメータ()の採用 |
| 保護装置 | /// の役割、整定方法、電力会社との協調 |
| 監視・制御装置 | 運転状態の監視項目、警報の種類、計測方法 |
| 変成器、変流器、零相変流器 | VT/CTの役割と定格検討項目 |
| 停電復電現象と対策 | 一時停電や瞬時電圧低下に対する設備の挙動と対策 |
| 接地工事 | A種・D種の適用と抵抗値、避雷器用接地極の取り扱い |
| キュービクルの配置と保有距離 | 点検・操作に必要な離隔距離の確保 |
| 認定キュービクル、推奨キュービクル | 設置目的によるキュービクルの選定基準と屋外設置時の法規 |
🔌 1. 高圧受電設備の結線図と使用機器
高圧受電設備は、電力会社から電気を受け取り、施設内で安全に使用するために必要な機器で構成されています。ここでは、設計図面や現場で使われる主要機器の略称と名称、そして制御回路で使用される制御器具番号をまとめました。
| 略称 | 名称 | 制御器具番号 (JEM1090) | 役割 |
| 電力需給用計器用変成器 | 電力計 () や力率計 () などに測定用の電圧・電流を供給 | ||
| 電力量計 | 使用電力量を積算・計量 | ||
| 断路器 | 無負荷の電路を開閉し、機器の点検・安全確保に使用(負荷電流は開閉しない) | ||
| 遮断器 | 事故電流(短絡・過負荷)や負荷電流を開閉し、電路を遮断・保護 | ||
| 変成器(計器用変圧器) | 高電圧を測定に適した電圧 () に変換 | ||
| 変流器 | 大電流を測定に適した小電流 () に変換 | ||
| 過電流継電器 | 過電流を検出し、遮断器 () に遮断信号を出力し、設備を保護 | ||
| 交流不足電圧継電器 | 電圧低下を検出し、遮断器 () に遮断信号を出力し、設備を保護 | ||
| 自動力率調整装置 | コンデンサを自動投入/開放し、設備全体の力率を改善 | ||
| 電圧計 | 電圧を測定 | ||
| 電流計 | 電流を測定 | ||
| 電力計 | 電力を測定 | ||
| 力率計 | 力率を測定 | ||
| 電圧切換開閉器 | 電圧計 () に加える電圧を選択 | ||
| 電流切換開閉器 | 電流計 () に加える電流を選択 | ||
| 電圧用試験端子 | の 次側回路の試験用端子 | ||
| 電流用試験端子 | の 次側回路の試験用端子 |
🛠️ 2. 設計手順(検討項目と要点)
受変電設備の設計は、短絡電流の検討が機器選定の鍵となります。以下の手順と要点をチェックしながら設計を進めてください。
短絡電流と機器・電線の選定
短絡電流の大きさによって、受電設備の主要機器の容量と電線の太さが以下のように決まります。特に短絡電流が大きい( 以下)場合は、機器の定格を上げる必要があります。
| 機器、電線 | 系統の短絡電流と機器の電気容量 |
| 以下 | |
| (注 ) | |
(注 )電線 () の最小太さの算出例
の式より、 で計算。
- ()の場合:
- ()の場合:
💡 3. 電力需給用計器用変成器(VCT)、電力量計(Wh)

や の設置場所は、電力会社との契約上、非常に重要です。設計時に以下の点を確認してください。
(1) 設置場所の検討要点
| 検討項目 | 要点 |
| 電力会社の機器手配 | 九州電力は電柱に取り付けることが多く、東京電力や関西電力など他の電力会社では受電設備内に取り付けることが多い。 |
| 引込み方式 | 地中引込みの場合は、、 ともに受電設備内に取り付ける。 |
| 設置スペース | 、 を受電設備内に取り付ける場合は、需要家側で設置スペースを確保する必要がある。 |

🛡️ 4. 断路器(DS: Disconnecting Switches / 89R)
断路器 () は、電路を切り離すためのもので、負荷電流を遮断する機能はありません。メンテナンスや安全確保のために、無負荷の電路を開閉する機器です。

⚙️(1) 断路器の定義と機能
断路器(Disconnector)は、高圧受電設備などで安全を確保するために欠かせない装置です。
ここでは、その定義と基本的な機能について整理します。
📘 定義
断路器とは、定格電圧のもとで「充電された電路」を開閉するための装置です。ただし、負荷電流の開閉を目的としない点が大きな特徴です。
つまり、断路器は電気的な絶縁を確保するための装置であり、開閉操作によって「この回路は安全に作業できる状態ですよ」と明確に示す役割を果たします。
💬 🐧見習いペン太:「はりたさん、断路器ってブレーカーみたいに電流を止める装置じゃないんですか?」
🦔 はりた:「いい質問だねペン太。でも断路器は“安全に電路を切り離す”ためのものなんだ。負荷がかかった状態で開けると危険なんだよ⚡」
🐧 ペン太:「なるほど、断路器は“見た目でわかる安全スイッチ”みたいなものなんですね!」
🔌 機能
断路器の主な機能は、
無負荷状態(電圧がかかっていない状態)の電路を安全に開閉することです。
-
メンテナンスや点検時に、電路を確実に遮断して安全を確保
-
作業中に誤って通電しないよう、物理的に絶縁状態を維持
-
開閉位置を目視できる構造により、安全確認が容易
⚠️ ただし、負荷電流が流れている状態では開閉できません。
アーク(電気火花)が発生して、機器損傷や感電事故につながるおそれがあります。
✅ ポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定義 | 定格電圧のもとに充電された電路を開閉する装置(負荷電流の開閉は不可) |
| 機能 | 無負荷状態の電路を安全に開閉し、点検や保守の安全を確保する |
🔎 ポイント
断路器は「遮断器」と混同されがちですが、目的がまったく異なります。
遮断器は電流を遮断する装置、断路器は安全な開放状態を確保する装置です。
(2) 規格、種類、表記事例

(3) 断路器の定格例
短絡電流への耐力を考慮した定格が定められています。


⚙️ (4) 断路器の選定要件と適用時の留意点
断路器を選定する際は、安全性と信頼性を確保するために3つの要件を満たす必要があります。
さらに、インターロックの有無を確認し、誤操作による感電や事故を防ぐようにしましょう。
✅ 断路器の3つの選定要件
| 要件 | 具体的な基準 |
|---|---|
| 定格電圧 | 系統の定格電圧を満足していること。 |
| 電流容量 | 最大負荷電流以上の電流容量を有すること。 |
| 短絡電流耐量 | 受電点の短絡電流以上の「定格短時間耐電流容量」を持つこと。 |
💡 選定例
たとえば、負荷電流が 100A の場合、通常は 定格200A の断路器で問題ありません。
しかし、もし短絡電流が8kAを超える場合には、定格400A以上のものを選定する必要があります。
💬 見習いペン太:「はりたさん、“短絡電流耐量”ってどうしてそんなに大事なんですか?」
🦔 はりた:「いい質問だねペン太。短絡(ショート)が起きた時、ものすごい電流が流れるんだ。断路器がその電流に耐えられなければ、焼損や爆発の危険があるんだよ⚡」
💬 ペン太:「なるほど…だから“短時間耐電流容量”をしっかり確認する必要があるんですね!」
🦔 はりた:「そう。定格電圧・電流・耐電流の3点セットを満たして、初めて“安全な断路器選定”ができるんだよ。」
📋 適用時のチェックポイント
- インターロックの動作を確認し、遮断器投入中は断路器を開閉できない構造であること。
- 機器の定格と系統条件が合致しているかを、受電点の短絡電流値で再確認する。
- 機器変更や回路改修時には、断路器の再選定を忘れずに行う。
- 断路器選定では「定格電圧・電流容量・短絡電流耐量」を必ずチェック。
- 条件を満たさないと、安全遮断ができず設備損傷の恐れあり。
- インターロック付き構造を選定し、作業者の安全を確保すること。
🚨断路器の適用時に注意すべきポイント
高圧受電設備などの設計・施工において、断路器(Disconnector) の設置は安全確保の基本です。点検や保守作業時に確実に電路を切り離せるよう、次の点に注意しましょう。
🔌 主遮断装置まわりのルール
主遮断装置の一次側には、
点検・安全のために必ず断路器を取り付ける必要があります。
たとえ遮断器が引出形(可動式)であっても、
一次側には断路器を設置するのが原則です。
⚙️ 分岐遮断器の場合の違い
-
固定式の分岐遮断器:
→ 必ず断路器を取り付けること。 -
引出形の分岐遮断器:
→ 必ずしも断路器を設ける必要はありません。
ただし、引出形から固定式に変更した場合は要注意!
断路器の追加を忘れると、安全上のリスクが生じます。
💬 見習いペン太:「はりたさん、引出形なら断路器なしでもいいんですか?」
🦔 はりた:「そうだね。引き抜くことで電路を物理的に遮断できるからね。でも固定式に変えたときは、断路器を忘れずに付けるのが大事だよ⚡」
💡 ペン太:「なるほど、形状によって“安全な遮断手段”が違うってことですね!」
| 区分 | 断路器の設置要否 |
|---|---|
| 主遮断装置の一次側 | 必ず設置 |
| 分岐遮断器(固定式) | 必ず設置 |
| 分岐遮断器(引出形) | 不要の場合あり |
| 引出形→固定式に変更 | 忘れず設置 |
断路器の設置有無は、保守点検の安全性に直結します。
設計変更や機器更新時には、必ず「断路器の有無」を再確認しておきましょう。
🏗️ 5. 主遮断装置の形式、受電設備方式、設備容量
受変電設備の形式は、主に設備容量と設置場所によって決定されます。

(1) 主遮断装置の形式と容量制限
主遮断装置には、遮断器()を用いる 形と、電力ヒューズ()と高圧交流負荷開閉器()を用いる 形の 種類があります。
特にキュービクル式の受電設備には、容量によって使用できる形式に制限があります。

(2) 受電形式の分類:開放式と箱式
| 形式 | 分類 | 定義と特徴 |
| 開放式 | 自立開放式 | 電気機器・装置を、鉄パイプで組みたてた枠(フレーム)に取り付けた受電設備です。機器がむき出しのため、広い設置面積と安全柵が必要です。 |
| 箱式 | 箱式 | 電気機器・装置を、鋼材で作成した箱内に取り付けた受電設備です。閉鎖型、キュービクル式、縮小形などがあり、設置面積を抑え、安全性が高いのが特徴です。 |
(3) 受電設備の施設場所と方法
受電設備の設置は、屋内式と屋外式に大別されます。
⚡ 6. CB形受電設備(Circuit Breaker)
形受電設備は、主遮断装置として**遮断器()**を使用した受電方式です。大容量・高信頼性の施設で採用されます。

⚡CB形受電設備の構成と選定ポイント
CB形受電設備とは、主遮断装置として遮断器(CB: Circuit Breaker)を用いた受電方式のことです。
ここでは、遮断器の種類・規格・選定条件をわかりやすく整理します。
🔍 遮断器の種類
高圧受電設備に使用される遮断器には、主に次の3種類があります。
- 磁気遮断器(MCB)
- ガス遮断器(GCB)
- 真空遮断器(VCB)
このうち、性能・価格・メンテナンス性のバランスから、
一般的には 真空遮断器(VCB) が採用されます。
💡 表記例:VCB 7.2kV 400A
💬 🐧見習いペン太:「はりたさん、“VCB”ってよく聞くけど、何が良いんですか?」
🦔 はりた:「真空中で遮断するから、アーク(火花)が発生しにくくて長寿命なんだよ!しかもメンテも楽なんだ✨」
⚙️ 遮断器の選定要件
遮断器を選定する際には、次の3つの条件を満たす必要があります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 定格電圧 | 系統の定格電圧を満足すること。 |
| 電流容量 | 最大負荷電流以上であること。 |
| 短絡電流耐量 | 受電点の短絡電流以上の「定格短時間耐電流容量」を持つこと。 |
💡 選定例
| 受電点の短絡電流 | CB定格電流 |
|---|---|
| 8kA以下(100MVA) | 400A |
| 8kA超〜12.5kA以下(160MVA) | 600A |
💬 🐧ペン太:「なるほど!短絡電流が大きいほど、定格の高い遮断器が必要なんですね。」
🦔 はりた:「その通り!機器が耐えられる電流を超えると、焼損や事故の危険があるんだ⚡」
🧩 ④ VCBとDS(断路器)の組み合わせ
VCBには断路機能がないため、通常はDS(断路器)と組み合わせて使用します。ただし、引出形VCB の場合は主回路接触部に断路機能を備えているため、主遮断装置が引出形であれば、DSを省略できる場合もあります。
💬 🐧ペン太:「つまり、固定式ならDSが必要で、引出形なら省略できるってことですね!」
🦔 はりた:「そうそう!ただし、省略できるかどうかは構造と安全性をよく確認してから判断するんだよ💡」
(3) その他の選定項目と引外し(トリップ)方式
遮断器の操作・制御方法によって、機種や引外し(トリップ)方式を選定します。
遮断器の選定項目
| 選定項目 | 標準 | 要望、打ち合わせによる方法 |
| 取付け方式 | 据置(固定)式(盤面取付け) | 引出形 |
| 操作方式 | 手動バネ式(投入電源無し・遠方操作しない場合) | 電動バネ式(投入電源が必要・遠方操作・自動制御等を行う場合)/電磁操作式 |
引外し方式と操作の詳細
保護継電器が事故を検出した際の遮断器の引外し方法は、制御電源や電圧の種類によって決定します。
| 引外し方式 | 略称 | 操作・電源 |
| 電圧引外し | 電源より供給。 の場合は と組み合わせて使用。 | |
| 不足電圧引外し | 電源より供給。電圧低下にて強制遮断。 | |
| 過電流引外し | 操作電源不要。 の電流により遮断。 | |
| コンデンサ引外し | コンデンサの放電エネルギーにより遮断。 |
注記: 保護継電器の種類によって引外し方式を合わせることが必要です。
- 過電流継電器 () および地絡継電器 () の場合は、電流引外し方式と電圧引外し方式の 種類があります。
- 地絡方向継電器 () の場合は、電圧引外し方式のみです。
💡 7. PF・S形受電設備(Power Fuse & Switch)
形受電設備は、主遮断装置に電力ヒューズ()を、開閉装置に高圧交流負荷開閉器()を使用した受電方式です。 以下の比較的小容量の施設で採用されます。

(1) 選定要件と容量制限
PF・S形(高圧限流ヒューズ付開閉器)は、
**キュービクル式の場合「300kVA以下」**で使用しなければなりません。
また、以下の条件を満たす必要があります。
-
電力会社との過電流保護協調が取れていること
-
高圧電動機を含まない設備であること
(2) 主遮断装置用限流ヒューズ(PF)の選定例
PF・S形受電設備では、変圧器容量に応じて限流ヒューズ(PF)を選定します。
| 変圧器種類 | 容量 | 推奨PF(例) |
|---|---|---|
| 単相変圧器 | 50kVA | G40(T20)A |
| 三相変圧器 | 100kVA | G40(T20)A |
※「G」は一般用、「T」は変圧器2次側用を意味します。
💬 ペン太:「なるほど、容量ごとにPFの定格が決まってるんですね!」
💬 はりた:「はい。選定を誤ると協調が崩れて、ヒューズが先に切れたりします。慎重に確認しましょう🐾」
PF・S形設備は、省スペース・省力化に優れていますが、容量や協調条件を誤ると重大なトラブルにつながります。LBSやPFの選定・設置は、電力会社との協議と法令遵守を前提に確実に行いましょう。
📈 8. 計器・計測器
高圧受電設備に取り付けることが標準とされる計器と、必要に応じてオプションで取り付ける計器があります。

(1) 標準とオプションの計器
| 分類 | 機器 | 略称 |
| 標準施設 | 電圧計、電流計、電力計、力率計 | または |
| オプション | 電力量計、周波数計、無効電力量計、最大需要電力計など |
(2) 電子式マルチメータの採用
電子式マルチメータとは、
電圧・電流・抵抗などの複数の電気量を1台で測定できる多機能計測器です。
最近では、以下のような理由から採用が増えています。
🔹 採用理由
- 省スペース化
- 配線作業の簡略化
- 点検・メンテナンスの効率化
- コスト削減(経済性)
🧊見習いペン太:「マルチメータって、電圧も電流もこれ1台で測れるんですね!便利そうです!」
🦔はりた:「そうなんだ。しかも最近のマルチメータは通信機能付きで、データを自動で集められるんだよ。省配線にもなるし、点検作業もラクになるのだ♪」
🧊見習いペン太:「なるほど、現場の省力化にもつながるんですね!」
🛡️ 9. 保護装置
保護装置(継電器)は、短絡や地絡などの電気事故時に、速やかに遮断器 () を動作させ、事故の拡大を防ぐための設備の守り役です。

(1) 過電流継電器()
| 項目 | 詳細な解説 |
| 役割 | 入力電流が整定値を超えた時に動作する継電器。(過電流には過負荷電流と短絡電流がある) |
| 構成 | (変流器)と (遮断器)と組み合わせて使用する。 |
| 整定 | 施工時は、** のタップ(動作電流整定)とレバー(動作時間整定)**を決定する。 |
| 協調 | 電力会社の保護装置は、リレーの動作整定値 以上の事故電流を 秒で遮断するため、自家用側の整定値はこれより短くし、保護協調を取る。 |
(1) 過電流継電器(OCR)とは
**過電流継電器(OCR:Over Current Relay)**は、
回路に流れる電流が設定値(整定値)を超えたときに動作する保護装置です。
過電流には、主に次の2種類があります。
-
過負荷電流:機器に負担をかける軽度の過電流
-
短絡電流:事故などによって発生する非常に大きな電流
💬 ペン太:「“過電流”っていっても、種類があるんですね!」
💬 はりた:「そうなんです。軽い過負荷と、ドンッとくる短絡では対処の仕方が違うんですよ⚡」
(2) 構成と動作の仕組み
OCRは、次の機器と組み合わせて使用します。
-
CT(変流器):電流を検出してOCRへ入力
-
CB(遮断器):OCRが動作信号を出すと遮断動作を実行
つまり、CTが「電流が多すぎる!」と知らせ、
OCRが「危ない!」と判断して、CBが「遮断!」と実際に動く仕組みです。
💬 ペン太:「みんなで協力プレーしてる感じですね!」
💬 はりた:「うん、まさにチーム保護装置ですね🐧」
(3) 整定(設定値)のポイント
施工時には、以下の2つを設定(整定)します。
-
タップ:動作電流の整定(何アンペアで動作するか)
-
レバー:動作時間の整定(どのくらいの時間で動作するか)
この設定によって、どの程度の過電流で・どれだけ早く遮断するかを決めます。
(4) 保護協調の考え方
電力会社側の保護装置は、リレーの動作整定値の約500%以上の事故電流を0.2秒で遮断します。
そのため、自家用設備のOCRはこれより早く動作するように整定し、
電力会社側との保護協調を取る必要があります。
💬 ペン太:「協調って、つまり“電力会社よりちょっと早く動くようにする”ってことですか?」
💬 はりた:「その通りです!お互いにタイミングをずらして動かすことで、
広範囲停電を防ぐんですよ🐧✨」
(2) 不足電圧継電器()
| 項目 | 詳細な解説 |
| 役割 | 電圧値が整定値以下になった時に動作する継電器。 |
| 整定値 | 動作電圧は定格電圧の 、動作時間は** 秒**に整定することが多い。 |
| 採用ケース | 復電時に順次起動する場合や、復電時自動運転すると危険な工場(大規模施設)などに、必要に応じて取り付ける。 |
| 機能 | 停電時には、高圧発電機に起動信号を出す。 |
(2) 不足電圧継電器(UVR)とは
**不足電圧継電器(UVR:Under Voltage Relay)**は、電圧があらかじめ設定した値よりも下がったときに動作する継電器です。
主に、電源トラブル時の安全確保や、復電時の制御に使用されます。
💬 🐧ペン太:「“不足電圧”って、電圧が下がりすぎた状態のことですよね?」
💬 🦔はりた:「そうそう。設備が正常に動かせないくらい電圧が下がると、自動で遮断したり警報を出したりするんですよ⚡」
(3) 整定の目安
不足電圧継電器の整定は、一般的に次の値が用いられます。
-
動作電圧:定格電圧の約 80%
-
動作時間:おおむね 2 秒
これにより、一時的な電圧降下では動作せず、
安定して電圧低下が続いた場合にのみ確実に反応します。
💬 🐧ペン太:「2秒っていうのは、ちょっと待ってから動作するってことなんですね!」
💬 🦔はりた:「うん、瞬間的な電圧のブレで誤作動しないようにしてるんだよ💡」
(4) 採用されるケース
不足電圧継電器は、以下のようなケースでよく採用されます。
- 停電復帰時に順次起動させたい設備
- 自動で復電起動すると危険な工場や大規模施設
- 高圧発電機を自動起動させる制御用として
停電が発生した場合には、
高圧発電機に「起動せよ!」という信号を出す機能も持っています。
💬 🐧ペン太:「なるほど、停電したら発電機に“出番ですよ!”って知らせてくれるんですね!」
💬 🦔はりた:「そういうことです🐧。安全に復電できるよう、影でしっかり働いてるんですよ。」
(3) 地絡継電器()
| 項目 | 詳細な解説 |
| 役割 | 地絡事故時に、整定値を超えた時に動作する継電器。 |
| 構成 | (零相変流器)と組み合わせて使用する。 |
| 整定 | 動作電流 、動作時間 秒に整定する。 |
| 協調 | 電力会社の地絡保護装置は、事故発生後 秒で動作するため、自家用側はこれより早く動作させ、協調を取る。 |
**地絡継電器(GR:Ground Relay)**は、地絡(アース故障)を検出して素早く系統を保護するための継電器です。
特に人の安全確保や設備の延焼防止に直結する重要な保護装置です。
📋 基本情報(一覧)
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 役割 | 地絡事故時に、設定した値を超えたときに動作して系統を遮断する。 |
| 構成 | ZCT(零相変流器:Zero-phase Current Transformer)と組み合わせて使用。 |
| 整定(目安) | 動作電流:200 mA / 動作時間:0.2 秒 |
| 協調 | 電力会社の地絡保護は事故発生後0.5秒で動作するため、自家用側はこれより早く(例:0.2秒)動作するよう整定して協調を取る。 |
🔎 解説ポイント
- 地絡は感電や火災につながるリスクが高いため、検出感度(動作電流)を低めに設定することが多いです。ここでは 200 mA を目安にします。
- 動作時間は 0.2 秒 程度に設定し、電力会社側の地絡保護(0.5 秒)より短く動作させることで、被害範囲を最小化します。
- 検出には ZCT(零相変流器) を用い、地絡が発生を検出します。
💬 🐧ペン太:「電力会社の装置より早く動かすっていう“協調”は、どうやって決めるんですか?」
🦔 はりた:「電力会社の保護特性を確認して、それより短い動作時間・適切な動作電流に整定することで決めるよ。設計時には電力会社と協議するのが大事なんだ⚡」
✅ 実務上の注意点
- ZCTの設置向きや二次配線の取り回しで検出精度が変わるため、取り付けと配線施工は丁寧に行う。
- 周囲のノイズ源(変圧器、モータ、スイッチング機器など)を考慮して、誤動作防止策(シールド、ツイストペア配線、適切な接地など)を施す。
- 設定値(200 mA / 0.2 s)はあくまで目安。設備の規模・用途・法令・電力会社指示に合わせて最終決定する。
(4) 地絡方向継電器()※波及事故防止!
**地絡方向継電器(DGR:Directional Ground Relay)**は、地絡電流の「方向」を判別して動作する継電器です。他の需要家からの波及事故を防止し、自需要家内での事故のみを確実に検出するために採用されます。
| 項目 | 詳細な解説 |
| 採用ケース | 地絡継電器()が不要動作する恐れがある時に採用する。 |
| 役割 | 地絡事故時に、地絡電流の方向性を判別し、整定値を超えた時に動作する継電器。 |
| 構成 | 、(零相電圧検出装置)と組み合わせて使用する。 |
| 整定 | 動作電流 、動作時間 秒に整定する。 |
🔎 解説ポイント
- 方向判別機能がポイント:ZCTで検出した地絡電流と、ZPDで検出した零相電圧の位相関係から、地絡が「自需要家側(順方向)」か「他需要家側(逆方向)」かを判別します。
- 他需要家の事故で誤動作を防ぐ:他需要家で地絡が発生すると、自需要家側にも地絡電流が流れ込み、通常のGRが誤動作する可能性があります。DGRはこの問題を解決します。
- 整定値(200 mA / 0.2 秒)はGRと同等ですが、方向判別により選択性が向上するため、自需要家内の事故のみを確実に検出し、不要な波及事故を防止できます。
💬 🐧見習いペン太:「はりたさん、DGRって普通のGRと何が違うんですか?」
🦔 はりた:「いい質問だね!整定値は同じだけど、DGRは電流の向きを見て判断するんだ。例えば隣の需要家で地絡が起きた時、自分の側のGRも反応しちゃうことがある。DGRなら”自分の需要家での事故かどうか”をちゃんと判別できるから、他需要家からの波及事故を防止できるんだよ。だから基本的には方向性の採用を優先しよう!🦔✨」
10. 監視・制御装置
監視・制御装置は、受電設備の運転状態の見える化と、異常時の迅速な対応のために必要です。

| 項目 | 監視・計測する内容 |
| 運転状態の監視 | 開閉器、遮断器類の開閉状態 |
| 警報 | 各種保護継電器の動作、高圧機器(:変圧器、:進相コンデンサ、:直列リアクトル)の異常、低圧回路漏電()の検出、電力ヒューズ () 溶断、低圧母線サーマルリレー () 動作 |
| 計測 | 電圧、電流、電力、力率、高調波電流 |
| 計量 | 電力量 |
| 監視・計測方法 | 中央監視装置、警報盤など |
💬 🐧見習いペン太:「はりたさん、監視項目がたくさんありますね!全部監視しないとダメなんですか?」
🦔 はりた:「いや、全部が必須ってわけじゃないんだ。設備の規模や用途、重要度に応じて必要なものを選択するんだよ。例えば小規模な施設なら警報盤で主要な故障監視だけでもOKだけど、大規模な工場やビルなら中央監視装置で全体を一元管理した方が効率的なんだ🦔✨」
💬 🐧ペン太:「デマンド制御って、具体的にどうやって電力を削減するんですか?」
🦔 はりた:「パルスピックで電力使用量を常に監視していて、契約電力を超えそうになったら事前に決めた対象機器(空調や照明など)を自動的に一時停止するんだ。削減量や制御対象は事前に計画して、電力会社とも協議して決めるよ。無理のない範囲で制御することが大事だね⚡🐧」
✅ 実務上の注意点
- 中央監視装置と警報盤の選択は、設備規模・管理体制・予算を考慮して決定する。大規模施設では中央監視装置による一元管理が推奨される。
- デマンド制御を導入する場合は、電力会社と事前協議し、パルスピックの取付け位置や制御方式を確認する。
- 制御対象機器の選定では、業務への影響が少ない機器(空調、給湯、照明など)を優先し、重要設備(サーバー、製造ラインなど)は制御対象外とする。
- 高調波電流の計測は、電力品質維持や進相コンデンサの保護に重要。特に高調波発生源(インバータ、LED照明など)が多い施設では必須。
- 監視・制御項目はあくまで目安。施設の用途・重要度・法令要求に合わせて最終決定する。
💡 11. 変成器(VT)、変流器(CT)、零相変流器(ZCT)
計器や保護継電器を動作させるために、高圧・大電流を変成する重要な機器です。

(1) と の仕様と選定
**変成器(VT:Voltage Transformer)と変流器(CT:Current Transformer)**は、高電圧・大電流を計器・計測器に適した値に変換する装置です。計測精度を確保し、安全に電圧・電流を監視するために不可欠な機器です。
⚠️ (2) 変流器(CT)の選定時の検討項目
**CT(変流器)**の選定では、定格負担、過電流強度、過電流定数の3つの項目を検討し、機器の性能を保証する必要があります。高圧受電設備では、一般的に推奨される基準値があります。
🔎 解説ポイント
定格負担は、CTの2次側に接続する計器・継電器の負担の合計値です。高圧受電設備では通常40VAあれば十分ですが、接続機器が多い場合は余裕を持たせます。
**過電流強度(定格耐電流)**は、短絡事故時の大電流にCTが耐えられるかを示します。高圧受電設備では定格1次電流の40倍が標準です。
過電流定数は、定格電流の何倍まで精度(比誤差10%以下)を保証できるかを示します。保護継電器の整定を考慮し、n>10(10倍以上)が標準です。
これら3つの項目をすべて満たすCTを選定することで、正常時の計測精度と事故時の保護性能の両方を確保できます。
💬 🐧見習いペン太:「はりたさん、過電流強度と過電流定数って似ていますけど、何が違うんですか?」
🦔 はりた:「いい質問だね!過電流強度は機械的・熱的な耐久性、過電流定数は計測精度の保証範囲を示すんだ。過電流強度40倍は『短絡電流が定格の40倍流れても壊れない』、過電流定数n>10は『定格の10倍まで誤差10%以内で計測できる』っていう意味だよ🦔✨」
💬 🐧ペン太:「高圧受電設備なら40VA、40倍、n>10でいいんですね。これより大きくする必要はありますか?」
🦔 はりた:「基本的にはこの標準値で問題ないけど、短絡容量が特に大きい系統や、接続する機器が多い場合は、過電流強度や定格負担を上げることもあるよ。逆に余裕を持たせすぎると精度が落ちたりコストが上がったりするから、必要十分な仕様を選ぶのが大事だね⚡🐧」
✅ 実務上の注意点
定格負担の選定では、接続する計器・継電器の負担を合計し、余裕率(1.2〜1.5倍程度)を考慮して選定する。
過電流強度は、系統の短絡容量計算結果と照合し、想定される最大短絡電流に耐えられることを確認する。
過電流定数は、保護継電器の整定値(特にOCRの動作倍率)を考慮し、整定範囲内で精度が保証されるよう選定する。
CTの2次側配線は太く短くし、接触抵抗を最小化することで負担を軽減し、精度向上につながる。
選定値はあくまで目安。系統条件・接続機器・保護協調に合わせて最終決定する。
🌎 12. 接地工事(安全確保の基本)
高圧受電設備における接地工事は、感電防止、機器の保護、電位上昇の抑制といった安全確保のために必須であり、 種と 種の 種類が主に用いられます。

| 接地工事の施設箇所 | 接地工事の種類 | 接地抵抗值 |
| ケーブルのシールド、高圧機器(、 など)の鉄台、及び金属製外箱、受電盤箱、 次回路、電力需給用計器用変成器外箱、電力量計 | 種 | |
| 避雷器(他の接地極と共用しない、単独接地とする) | 種 | |
| 及び 次回路、 次回路、 次回路、キュービクル外箱 | 種 |
注記: 最近は 種と 種の接地工事を共用する場合が多いです。
📏 13. キュービクルの配置と保有距離
キュービクルの配置にあたっては、保守・点検作業の安全性と効率を確保するため、**離隔距離(保有距離)**を確保することが電気設備技術基準で義務付けられています。

(1) キュービクル本体の保有距離の基準
| 保有距離を確保する部分 | 保有距離 [m] | 解説 |
| 点検を行う面 | 以上 | 内部機器の点検・調整に必要な最低限のスペース。 |
| 操作を行う面 | +保安上有効な距離以上 | 開閉器や遮断器の操作、計測などを行うスペース。 |
| 溶接などの構造で換気口がある面 | 以上 | 換気口から熱気や排気が出るため、最低限のスペースを確保します。 |
| 溶接などの構造で換気口がない面 | 離隔距離は不要です。 |
(2) 受電設備に使用する配電盤などの最小保有距離
キュービクル内部や受電室内の高圧・低圧配電盤、変圧器などの機器配置についても、安全な作業空間を確保するための最小離隔距離が定められています。(単位:)
| 部位別・機器別 | 前面 又は 操作面 | 背面 又は 点検面 | 列相互間 (点検を行う面) | その他の面 |
| 高圧配電盤 | ||||
| 低圧配電盤 | ||||
| 変圧器類など |
(注)「列相互間」は機器類を 列以上設ける場合をいいます。
🚨 注意事項
- 高所設置の対策: キュービクルを高所の開放された場所に施設する場合、周囲の保有距離が を超える場合を除き、高さ 以上の柵を設けるなどの墜落防止措置を施します。
🔥 14. 認定キュービクル、推奨キュービクル
キュービクルには、その用途と目的によって、一般社団法人日本電気協会が定めた認定基準と推奨基準があります。

(1) 認定キュービクルの定義
認定キュービクルは、消防法第 条に定める消防設備等の電源を確保するため、(一社)日本電気協会が制定した「キュービクル式非常電源専用受電設備認定基準」に適合した、特に信頼性の高いキュービクルです。
(2) 推奨キュービクルの定義
推奨キュービクルは、自家用高圧需要家受電設備の安全確保及び電気事業者への波及事故を防止するため、(一社)日本電気協会が制定した「キュービクル式高圧受電設備推奨基準」に適合したキュービクルです。
(3) 屋外における受電設備の設置例(消防法第 条関連)
屋外に受電設備を設置する場合、火災予防の観点から建築物との離隔距離が定められています。
- 原則: 屋外に設置する場合は、建築物から 離す必要があります。
- 例外: 受電設備と面する部分が不燃材でつくられていれば とすることができます。
- 届出: 設置前には、所轄の消防署と事前に打ち合わせを行う必要があります。
(4) 設置場所検討の留意事項
- キュービクルの設置にあたっては、電気設備技術基準の解釈に加えて、消防法や建築基準法、自治体の条例などを確認する必要があります。
- 特に、消防法上の危険物施設やガス設備などからの離隔距離も、別途考慮しなければなりません。
🔎 解説ポイント
- 認定キュービクルは、消防設備専用の電源として高い信頼性が要求されるため、推奨キュービクルよりも厳格な基準に適合している必要があります。
- 推奨キュービクルは、一般的な高圧受電設備として、安全性と波及事故防止性能を満たした標準仕様です。
- 屋外設置時の離隔距離は、火災予防の観点から消防法で定められています。建築物との距離は原則3mですが、不燃材を使用すれば1mに短縮できます。
- 設置前の届出は必須で、所轄消防署との事前打ち合わせを通じて、設置位置や離隔距離の確認を行います。消防法、建築基準法、自治体条例などの複数の法規制を総合的に確認する必要があります。
💬 🐧見習いペン太:「はりたさん、認定キュービクルと推奨キュービクルって、どう使い分けるんですか?」
🦔 はりた:「認定キュービクルは消防設備専用の電源として使うんだ。非常用照明やスプリンクラーとか、火災時に絶対止まっちゃいけない設備の電源だね。推奨キュービクルは一般的な受電設備として使うよ。用途に応じて選ぶんだ🦔✨」