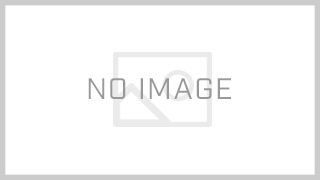1. 高圧変電・配電設備の結線図と使用機器
1.1 結線図の種類と選定
高圧受電設備において、どのような結線図を採用するかは、受電方式(単回線、予備線、スポットネットワークなど)によって決定されます。
- 検討における重要な要点: 設備の信頼性、経済性、そして将来的な拡張性を総合的に考慮して選定を進めます。
- 記載内容: 代表的な結線図(単線結線図)の例を示し、選定理由を明確にすることが一般的です。
1.2 主な使用機器(機器記号リスト)
本設備で使用される主要な機器の記号、名称、およびその概要・役割は以下の通りです。
| 記号 | 機器名称 | 概要・役割 |
|---|---|---|
| L B S | 高圧交流負荷開閉器 | 高圧回路の開閉を目的として使用されますが、故障電流を遮断する機能は備えていません。 |
| P C | 高圧カットアウト | 高圧回路用のヒューズと開閉器を組み合わせた装置です。 |
| P F | 電力ヒューズ | 短絡事故などの際に、速やかに溶断することで回路と機器を保護します。 |
| T | 変圧器 | 受電した高電圧を、負荷設備で使用するために適切な低電圧に変換する機器です。 |
| S C | 進相コンデンサ | 負荷の力率を改善し、電力損失の低減や電圧の安定化に貢献します。 |
| S R | 直列リアクトル | 進相コンデンサ投入時に発生する高調波電流を抑制するために設けられます。 |
| Z C T | 零相変流器 | 地絡電流を検出し、その情報を保護継電器に送る役割を担います。 |
| E L | 漏電継電器 | 零相変流器からの情報に基づき地絡事故を検出し、遮断器へ動作指令を出します。 |
| L G R | 低圧漏電警報器 | 低圧回路で地絡事故が発生した際に警報を発報する装置です。 |
| C T | 変流器 | 大電流を測定・保護のために必要な小電流に変換し、保護継電器や計器に供給します。 |
| T H R | サーマルリレー | モータなどの過負荷(熱的な故障)を保護するために使用される継電器です。 |
| V、A | 電圧計、電流計 | 回路の電圧や電流を測定し、表示するための計器です。 |
| V S | 電圧切換スイッチ | 電圧計を用いて複数の相間電圧を切り替えて測定するためのスイッチです。 |
| A S | 電流切換スイッチ | 電流計を用いて各相の電流を切り替えて測定するためのスイッチです。 |
| M C C B | 配線用遮断器 | 低圧幹線や負荷回路の過負荷・短絡事故発生時に回路を遮断し、保護します。 |
| E L C B | 漏電遮断器 | 低圧回路の地絡電流を検出し、自動的に回路を遮断し保護する機能を持っています。 |
2. 設計手順(主な検討項目と要点)
高圧受電設備の設計は、以下の主要な手順と要点を踏まえて進めることが推奨されます。
| No. | 検討項目 | 要点 |
|---|---|---|
| 1 | 設計負荷容量の算定 | 竣工建物による想定や詳細な負荷集計に基づき、施設に必要な最大需要電力を適切に推定します。 |
| 2 | 受電電圧・容量の決定 | 電力会社との契約電力や、将来の負荷増設見込みを考慮して、最適な受電電圧と契約容量を決定します。 |
| 3 | 保護協調の検討 | 事故発生時の影響拡大(波及)を防止するため、継電器の最適な動作時間や整定値を決定することが重要です。 |
| 4 | 短絡電流計算 | 機器の遮断容量や耐短絡強度が、想定される短絡電流に対して十分であることを確認します。 |
| 5 | 設置スペースの確保 | キュービクルの寸法や質量を考慮し、将来の保守点検に必要なスペースを適切に確保する必要があります。 |
3. 設備負荷容量の算定
3.1 設計負荷の集計方法
変電設備の容量を決定する際は、単相負荷、三相負荷それぞれについて、幹線ごとに集計することが基本となります。
(1) 設計負荷の集計項目
変圧器容量や幹線サイズを決定するために、以下の種類ごとに負荷容量を算定します。
| 負荷種別 | 対象設備例 | 検討要点 |
|---|---|---|
| ① 単相負荷 | 分電盤負荷(照明、コンセント、OA用、その他)、専用負荷 | 各相へのバランスを考慮し、不平衡率が30%以下になるよう配慮することが重要です。 |
| ② 三相負荷 | 動力盤負荷(空調機、ポンプ、ファン等)、専用負荷(エレベーター、レントゲン、製造装置等) | 起動電流(始動電流)が定格電流に与える影響を考慮する必要があります。 |
| ③ スコット変圧器負荷 | 分電盤負荷、保安照明・コンセント、非常照明(単相負荷) | 一次側の三相平衡を確保したうえで、単相負荷に電力を供給します。 |
(2) 竣工建物からの想定(電力原単位による概算)
平面図を設計する前の計画段階で受変電設備等を計画する場合は、過去に竣工した類似の建物から分析されたデータに基づいて容量を概算します。
検討における重要なデータ:
- 電力原単位(例:延べ床面積 以上 未満の建物など)
- 負荷設備の密度表 など
これらの実績値を基に、設計の初期段階で概略の容量を推定することができます。
3.2 変圧器容量の決定
各変圧器バンクが負担する最大需要電力を計算し、変圧器の定格容量を決定する必要があります。
【変圧器容量の計算式】 変圧器バンク容量 >= 設備容量 x 需要率 x (1 + 増設予備率)
(1) 需要率の考慮
変圧器容量を決定する際には、すべての設備が一斉に最大使用されることはないため、建物の用途に応じた適切な需要率を考慮して容量を決定することが一般的です。
- 記載内容: 用途別(例:事務所、店舗、工場など)の標準的な需要率を参考にします。
(2) 負荷率・不等率の定義
負荷容量の決定に用いる負荷率や不等率についても、その定義と適用する値を明確にしておく必要があります。
- 検討要点: 許容過負荷運転能力、力率改善後の容量、今後の負荷増設余地を考慮に入れます。
4. 変圧器の選定と詳細
4.1 規格および種類
(1) 適用規格
変圧器を選定する際は、以下の規格に適合するものを選ぶ必要があります。
- J I S C 4304、4306
- J E C 2200
- J E M 1482、1483
(2) 種類と構造
- 種類: 単相、三相
- 構造: 油入り、モールド、乾式
- 選定基準: 特にご要望がない場合は、原則として油入り変圧器を標準といたします。防火上の制約や、設置環境(湿度、粉塵など)を考慮して、モールド式や乾式を選定することも可能です。
4.2 定格一次・二次電圧、標準結線
変圧器の定格一次・二次電圧と標準的な結線は、以下の表を参考にしてください。
| 相数・線数 | 一次電圧 [V] | 二次電圧 [V] (周波数) | 三相変圧器の標準結線 |
|---|---|---|---|
| 単相3線式 | 6600 | 210 ・ 105 (50, 60Hz) | — |
| 三相3線式 | 6600 | 210 (50, 60Hz) | Y-Delta (星形-三角) |
| 三相3線式 | 6600 | 420 (50Hz) | Delta-Y (三角-星形) |
| 三相3線式 | 6600 | 440 (60Hz) | Delta-Y (三角-星形) |
4.3 容量、台数、バンク構成の決定
(1) 容量選定
- 容量計算の原則: 変圧器容量の計算時には、需要率を考慮して余裕のある容量を選定します。
- 負荷の考慮: 負荷の種類(空調、換気、衛生負荷など)や設置位置(階数)、幹線経路などを考慮して、変圧器の容量を決定します。
- 定格容量の選定: 合計負荷容量を基に、下記のJIS規定の定格容量(単位 kVA)から選定することが一般的です。
(2) 台数と短絡電流の関係
- 三相変圧器は、単体でご使用いただいても不平衡になることはありませんので、上記の標準容量の範囲内で選定いただけます。
- ただし、容量が大きくなると、それに伴い短絡電流も大きくなります。これにより、低圧配電盤の遮断器(MCCBなど)の遮断容量が増加し、機器の価格が高くなる点に注意が必要です。
(3) 三相変圧器の定格容量別一次・二次結線
JISに規定されている三相変圧器の定格容量ごとの標準的な結線は下表の通りです。
| 定格容量 (kVA) | 一次結線 | 二次結線 |
|---|---|---|
| Y | Y | |
| Y | Delta | |
| Y | Delta | |
| Delta | Delta | |
| Y | Y (中性点端子付き) | |
| Delta | Delta |
4.4 スコット変圧器(V-V結線も含む)
(1) 概要(用途)
- 名称の由来: この変圧器を発明した物理学者「スコット」にちなんで名付けられました。
- 主な用途: 三相電源から単相電源を2回線で取り出す場合に用いられます。
- その他: 発電機回路や単相負荷接続時など、一次側の三相平衡を確保したい場合にも使用されます。
(2) 結線と容量の考え方
- 結線構成: 主座(M座)変圧器とT座変圧器の2台で構成されます。
- 容量の原則: 単相回路は必ず2回線に分け、等容量(P1 = P2)になるように接続することで、一次側の三相平衡を確保することができます。
- 合計容量: スコットトランス容量 P = P1 + P2
- 二次側回路: 単相2線2回線、又は単相3線2回線のいずれでも設計が可能です。
(3) 容量選定とその他
- 定格容量の選定: 合計負荷容量を基に、下記の標準容量(単位 kVA)から選定します。
- トップランナー型: スコット変圧器にはトップランナー型変圧器の規定はありません。
- 中性点接地: 低圧側の中性点の接地は共用できます。中性点接地は、地絡時の電位上昇の抑制、低圧側の対地電圧の制限、そして保護装置(漏電リレー)の確実な動作のために重要です。
4.5 始動共用変圧器(V結線変圧器)
(1) 概要
電灯用(単相)と動力用(三相)の電源を1台の変圧器で供給できるように、巻線の途中から分岐をもたせた変圧器のことを指します。
(2) 等容量V結線変圧器(Open-delta connection)
容量が等しい単相変圧器を2台用いたV結線(Delta結線から1相を取り除いた結線)です。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| V結線出力 | ルート3 x E x I となります(E: 線間電圧、I: 変圧器巻線電流)。 |
| 変圧器利用率 | 変圧器2台の出力に対し、利用率は ルート3 / 2、すなわち**約 86.6%**となります。 |
(3) 異容量V結線変圧器(Unlike capacity Open-delta connection)
- 概要: 容量が異なる単相変圧器を用いたV結線の変圧器です。
- 用途: 単相負荷と三相負荷の両方の電力を同時に供給したい場合に用いられます。
4.6 変圧器一次側開閉器の選定
変圧器の一次側に設置する開閉器は、下表の適用区分に従い、開閉装置を設けます。設計時には、高圧交流負荷開閉器(LBS)を標準とすることが多いです。
| 変圧器容量 | 遮断器(CB) | 高圧交流負荷開閉器(LBS) | 高圧カットアウト(PC) |
|---|---|---|---|
| 300kVA以下 | |||
| 300kVA超過 |
は施設可能、は施設できないことを示します。
4.7 温度上昇と冷却方式
変圧器の冷却方式(自冷式、風冷式など)と、許容される温度上昇の基準について適切に記載する必要があります。(この項目は現状維持といたします。)
4.8 励磁突入電流とその対策
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 励磁突入電流 | 変圧器に電圧を印加した瞬間に、定格電流の**倍もの大電流**が流れる現象をいいます。 |
| 問題点 | 主遮断器を投入する際、この励磁突入電流によりOCR(過電流継電器)が誤って動作する恐れがあるため対策が必要です。 |
| 対策例 | 1. 変圧器一次側に限流抵抗や限流リアクトルを設置します。 |
| 2. 変圧器をグループに分け、時間差で順次投入する方法が最も多く採用されています。 | |
| 3. 磁束密度を低減した変圧器を採用することも有効です。 |
4.9 選定時の付帯的な検討事項
変圧器を選定するにあたっては、容量や電気的特性のほかに、以下の項目についても多角的に検討を行うことが求められます。
| 検討項目 | 検討内容 |
|---|---|
| 防振対策 | ・防振装置の取り付け(防振ゴム、バネ式防振装置など)を実施し、振動伝達率を低減させるよう努めます。 |
| 騒音対策 | ・騒音源:変圧器本体や換気装置(ファンの騒音)を特定します。 |
| ・電気室の壁による防音対策を施すことが一般的です。 | |
| 換気設備 | ・受電設備の主な発熱源は変圧器による発熱量が最も大きいため、電気室やキュービクルの換気設備を設計する際は、変圧器の排熱量を主として検討を進めます。 |
| ・キュービクルが面ごとに仕切られている場合は、面ごとに排熱量を計算する必要があります。 | |
| 消火設備 | ・消防法に基づき、消火設備の設置義務があるかを確認し、適切に施設します。 |
| ・発変電設備における消火設備例:高圧受電設備規程 P390に基づく特殊消火設備、大型消火器、消火器などが挙げられます。 |
5. 進相コンデンサの設計
5.1 設置目的と効果
進相コンデンサを設置する目的は、力率を改善することであり、これにより以下の通り、様々な経済的・技術的なメリットを得ることができます。
- 線路損失の低減:力率改善により電流が減少し、抵抗損失 (I^2R) が抑えられます。
- 電圧降下の低減:電流の減少に伴い、線路や変圧器における電圧降下が抑制され、電圧の安定化に寄与します。
- 電流の減少による設備余力の発生:変圧器や配線路に余裕が生まれ、将来の負荷増設に備えることができます。
- 高調波電流の流出の抑制:適切な設計により、高調波電流の抑制にも役立つ場合があります。
- 力率割引による電気料金の基本料金の低減:電力会社との契約に基づき、力率が改善されることで電気料金の基本料金が割引されます(または割増を回避できます)。
5.2 規格および種類
(1) 適用規格
- 進相コンデンサはJ I S C 4902-1に適合するものを選定する必要があります。
(2) 種類と構造
- 種類: 油入り、乾式(窒素ガス絶縁、SF6ガス絶縁)
- 選定基準: 特にご要望がない場合は、油入りを標準といたします。
5.3 容量の算定と選定
(1) 容量算定の考慮事項
- 負荷の力率、使用時間、使用季節などを総合的に考慮し、過補償にならないよう最適な容量を決定します。
- インバータ式空調機などの高調波発生機器の負荷は、コンデンサ容量の計算には含めないことが一般的です(高調波対策を別途検討する必要があるため)。
【進相コンデンサ容量の計算式】 進相コンデンサ容量 (kvar) = 有効電力 (kW) x (tan θ1 - tan θ2)
- : 力率改善前の位相角
- : 力率改善後の目標位相角
(2) 一次側開閉器の選定
進相コンデンサの一次側には、下表の適用区分に従い開閉装置を設けます。設計時は、高圧交流負荷開閉器(LBS)を標準とすることが多いです。
| 機器種別 | 開閉装置 |
|---|---|
| 定格設備容量 | CB (遮断器) |
| 50kvar以下 | |
| 50kvar超過 |
は施設可能、は施設できないことを示します。
は施設可能ですが、進相コンデンサ容量の定格設備容量を運用上変化させる必要がある場合にはCBもしくはVMCの採用が推奨されます。
定格設備容量 50kvar は、直列リアクトル 6%付きの場合、コンデンサの定格容量としては 53.2kvar となります。
- 検討要点: 過補償による異常電圧上昇や、自家用発電設備との協調についても検討が必要です。
5.4 容量の分割と制御方式
(1) 容量の分割
進相コンデンサの定格設備容量が300kvarを超過する場合は、2群以上に分割することが求められます。これは、負荷の変動に応じて接続する進相コンデンサの定格容量を変化させられるようにするためです。
(2) 開閉装置の選定
開閉ひん度が多い箇所では、開閉寿命の長い開閉装置(VMC:真空接触器)を使用することが推奨されます。
(3) 保護装置
進相コンデンサの一次側には、限流ヒューズを施設します。
(4) 残留電荷の放電
コンデンサ回路には、コンデンサ容量に適合する放電コイル、または開閉路後の残留電荷を放電させるための適切な装置を設ける必要があります。
ただし、以下の場合は放電装置を省略することができます。
- コンデンサが変圧器の1次側に直接接続されている場合。
- 放電抵抗が内蔵されたコンデンサを用いる場合。
【放電抵抗と放電コイルの規定】
| 種類 | 放電抵抗 (DisCharge Resistor) “DCR” | 放電コイル (DisCharge coil) “DCC” |
|---|---|---|
| 規定 | 印加電圧開放後5分以内にコンデンサの端子電圧を50V以下に下げるよう定められています(低圧用の場合は3分以内とされています)。 | 印加電圧開放後5分以内にコンデンサの端子電圧を50V以下に下げるよう定められています。 |
- 放電コイルは直列リアクトルの1次側に設置されることがあります。
- 放電コイルは計器用変圧器(VT)を使用している場合があります。
5.5 制御機器の開閉回数(寿命目安)
(1) コンデンサの開閉回数(目安)
連続開閉後の休止: コンデンサは5秒間隔で連続5回の開閉を行った場合、約6時間の休止が必要とされています。
年間開閉回数目安:
低圧進相コンデンサ:5,000回/年
高圧進相コンデンサ:4,000回/年
(2) VMC(真空接触器)の開閉回数(耐久性)
| 項目 | 対象負荷 | 耐久回数 |
|---|---|---|
| 電気的開閉耐久性 | 電動機、変圧器 | 25万回 |
| コンデンサ | 10万回 | |
| 機械的開閉耐久性 | 常時励磁式 | 250万回 |
| 瞬時励磁式 | 25万回 |
6. 直列リアクトルの設計と特性
6.1 規格および設置目的
(1) 適用規格
- 直列リアクトルはJ I S C 4902-2 (2010)(高圧及び特別高圧進相コンデンサ並びに附属機器−第 2 部:直列リアクトル)に適合するものを選定します。
(2) 設置目的(施設勧告)
進相コンデンサには、以下の目的のために、直列リアクトルを施設すること(勧告)が定められています。
- 高調波電流による障害防止
- コンデンサ回路の開閉による突入電流抑制
6.2 容量の算定と選定
直列リアクトルは、回路が高周波に対して誘導性になるように容量を選定します。その容量は、回路に含まれる高調波の次数によって決定されます。
| 抑制対象となる高調波 | 選定容量(SC容量比) | 計算根拠(誘導性条件) |
|---|---|---|
| 第5高調波が主要な場合 | 進相コンデンサの6% | 共振周波数を回避するため、インダクタンスLはコンデンサ容量Cの4%以上(余裕を見て6%)とすることが推奨されます。 |
| 第3高調波が多い場合 | 進相コンデンサの13% | 共振周波数を回避するため、インダクタンスLはコンデンサ容量Cの11%以上(余裕を見て13%)とすることが推奨されます。 |
6.3 最大許容電流と高調波含有率
直列リアクトル回路に高調波電流が含まれる場合、故障なく使用できる合成電流の実効値の限度(最大許容電流)は下表に基づき決定されます。
| 許容電流種別 | 最大許容電流 (定格電流比)% | 第5調波含有率 (基本波比)% | 適用 | 電圧ひずみの上限目標値 |
|---|---|---|---|---|
| I | 120 | 35 | 特別高圧受電設備用 | 総合: 3%、第5調波: 2.5% |
| II | 130 | 55 | 高圧配電系用 | 総合: 5%、第5調波: 4.0% |
- 許容電流種別 I は、主として特別高圧受電設備に適用されます。
- 許容電流種別 II は、主として高圧受電設備に適用されます。
6.4 警報回路と温度種別
(1) 警報回路
直列リアクトルは警報接点付きとし、異常が発生した際には警報を発するとともに、自動的に回路を開放できる構造であることが求められます。
(2) 温度種別と構造
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 温度種別 | 回路電圧 3300V、6600V |
| 構造の選定 | 直列リアクトルを屋内で使用する場合、進相コンデンサと温度特性を整合させるために乾式モールド式を使用する必要があります。 |
6.5 定格電圧と定格設備容量の計算例
直列リアクトル(L=6%の例)を接続した場合の、進相コンデンサと直列リアクトルの定格値は以下のように計算されます。これは、直列リアクトルにより電圧が上昇するためです。
| 項目 | 計算式 | 6600V 回路、定格設備容量 100kvar の場合 |
|---|---|---|
| ① 進相コンデンサの定格 | ||
| 定格電圧 VQ | VQ = 回路電圧 / (1 - L/100) |
6600 / (1 - 6/100) ≒ 7020 [V] |
| 定格容量 Q | Q = 定格設備容量 / (1 - L/100) |
100 / (1 - 6/100) ≒ 106 [kvar] |
| ② 直列リアクトルの定格 | ||
| 定格電圧 VSR | VSR = {(回路電圧/ルート3) / (1 - L/100)} x L/100 |
{(6600 / ルート3) / (1 - 6/100)} x 6/100 ≒ 243 [V] |
| 定格容量 SR | SR = {定格設備容量 / (1 - L/100)} x L/100 |
{100 / (1 - 6/100)} x 6/100 ≒ 6.38 [kvar] |
【記号の定義】
- VQ : コンデンサ定格電圧
- Q : コンデンサ定格容量
- VSR : 直列リアクトル定格電圧
- SR : 直列リアクトル定格容量
- L : 直列リアクトルの百分率(%)
7. 高圧送出回路の施設基準
7.1 回路の構成と保護
本回路は、キュービクルからサブ変電所などの他の高圧設備へ電力を送出する回路に関する基準です。高圧送り出し回路の施設は、次によります。
(1) 保護装置の設置原則
高圧送出回路には、原則として以下の2つの保護装置を施設することが義務付けられています。
- 過電流保護装置(CT + OCR、又はPF)
- 地絡保護装置(ZCT + GR)
- 長距離ケーブルの対策: 高圧送出回路のケーブルが長い場合、地絡保護装置の不要な動作を防止するため、方向性地絡継電器(ZCT + DGR + ZPD)を用いることが推奨されます。
(2) 主遮断装置と送出制限
主遮断装置がP F・S形(電力ヒューズと高圧開閉器の組み合わせ)の場合は、高圧電動機への送り出しは行わないようご注意ください。
- 理由: P F・S形は、電動機の始動時の大きな突入電流や、電動機の地絡・相間短絡に対する保護協調をとることが難しいためです。通常は**VCB(真空遮断器)**などを介した保護リレー構成が必要です。
(3) 地絡保護装置の省略条件
屋内型であって、同一電気室内に送り出す場合は地絡保護装置(GR)を省略できるとされています。
7.2 ケーブル選定
- 検討要点: 許容電流、電圧降下、短絡電流に対する熱的・機械的強度、敷設方法(直埋、管路、ラックなど)について詳細に検討する必要があります。