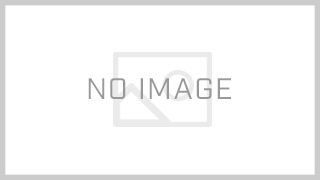ビルや施設の配線計画で欠かせないケーブルラック。中でも**立上りタイプ(縦方向に設置されるラック)**については、地震対策として特別な配慮が必要です。
この記事では、「建築センター指針」に基づいたケーブルラック立上り耐震支持の考え方・施工の原則・対策方法をわかりやすく解説します。
✅ ケーブルラック立上りの耐震支持とは?
ケーブルラックの立上りに対しても、横引き(水平設置)と同様に、以下のような分類で耐震強度を評価します。
-
SA種耐震支持
-
A種耐震支持
※立上り構造では、吊りボルトによる支持は不可のため、「B種耐震支持」は対象外です。
📌 設置の基本ルール
EPS(電気配線シャフト)などで縦に設置されたケーブルラックは、以下の基準で支持を行います。
| 項目 | 基準内容 |
|---|---|
| 支持間隔 | 原則「6m以内」 |
| 各階での支持 | 各フロアごとにしっかり支持を取る |
| 継ぎ金具 | 負荷集中に備え「補強タイプ」を使用する |
⚠️ 支持間隔が広いとどうなる?
階高(フロアの高さ)が大きい建物では、各階の支持点の間隔が開いてしまい、継ぎ手部分に過大な荷重が集中する恐れがあります。
その対策として、次のような工夫が必要です。
🔧 対策方法
-
ブレース(補強材)で補強する
→ 設置手間は増えるが、スペースが限られる場合や既設ラックにも有効

-
支持間隔を短くする
→ 壁や天井にも耐震支持を追加し、6m以内に分割する
📌 特に階高が6mを超える場合は、「支持間隔6m以内」を守る必要があります
6mを超える場合には、中間にブラケットを壁から支持しケーブルラックを固定します。
この場合、支持間隔は耐震架台の上部からブラケット間の距離になります。
詳しい図はネグロスのカタログをご参照ください
🔍 なぜ“6m以内”が重要なのか?各階での支持が必要な理由
ケーブルラック(特に立上り=縦方向の配線経路)は、建物の複数階にわたって電線を通す構造です。
このような構造では、地震の揺れによる上下の振動やケーブルの自重が、ラック自体に大きな負担をかける可能性があります。
そのため「耐震支持の基本ルール」として、次の2点が原則とされています:
✅ 原則1:支持間隔は“6m以内”
これは、ラックがしなる・倒れる・継ぎ目が壊れるなどのリスクを避けるための基準です。
✅ 原則2:各階でしっかり固定する
特にEPS(電気配線シャフト)やPS(パイプスペース)など、建物内の縦配線スペースでは、フロアごとにケーブルラックを建物構造体に固定することが求められます。
● 各階で固定するメリット:
-
ラックの倒れや揺れを抑えられる
-
重量物ケーブルの積載によるたわみを防止
-
階ごとの揺れの周期差による共振リスクを分散できる
📌 もし6m以上になってしまう場合の対応は?
階高が高い工場や大型施設では、やむを得ずラック支持間隔が6mを超えるケースもあります。
その場合は以下のような補助対策が必要です:
| 対策方法 | 内容例 |
|---|---|
| 壁・天井面にも支持追加 | 中間部で振れ止め(ブレース)を設置して支点を増やす |
| 支持金具の補強 | 通常の継ぎ金具ではなく補強タイプを使用 |
| ラック自体の強度UP | 耐震等級の高い(厚鋼製などの)重耐震ラックに変更 |
🚫 ALC壁に注意!
ALC(軽量気泡コンクリート)パネル壁は地震で壊れやすいため、耐震支持の固定部材には不適切とされています。
できるだけRC梁や柱などの構造躯体に固定することが推奨されます。
✅ まとめ
-
ケーブルラック立上りも、SA種・A種支持で設計する必要がある
-
支持間隔は原則6m以内、各階でしっかり固定すること
-
継ぎ金具には補強タイプを使用
-
支持方法の選定には、設備の重量・階高・設置スペースを考慮
-
状況に応じて「ブレース追加」「支持間隔の調整」で対処