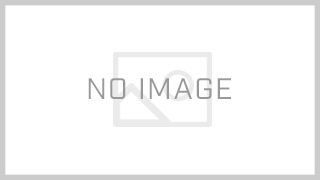はじめに:緊張感のある現場で、どう育てるか
私が若手だった頃、先輩たちがいつも真剣な表情で仕事をしている姿を見て、「質問していいのかな」と遠慮してしまうことがよくありました。緊張感のある現場では、どうしても空気がピリッとしてしまうものです。
そして、私自身が人を育てる立場になったとき、同じような悩みに直面しました。若手に経験を積んでほしい。でも、大きなミスは避けたい。この「任せたいけど心配」という気持ちは、きっと多くの先輩が感じているのではないでしょうか。
私が大切にしている、仕事の任せ方
若手に仕事を任せるときに、私がいつも心がけていることが二つあります。
1. 「チャレンジしやすい」仕事から始める
若手に仕事を教えるとき、私は下記のようなものから優先して依頼することを意識しています。もし失敗しても、すぐにカバーできる仕事から始めるということです。
・参考図があるもの
・同じものを一度自分でやっているもの
・答えが明確にあるもの
・納期が長いもの
・先方への提出に直接的でないもの
自身の経験から、「この仕事だと、このポイントでつまずくだろう、この資料を必ず見るはずだろう。この時間くらいには終わってくるだろう」とあらかじめ想像した上で依頼し、実際にどのような取り組みをしているかをなんとなくで見ています。
2. 相談しやすい文化を作る
報連相をしやすい環境を作るために、私が最も意識しているのは、若手の発言を絶対に否定しないことです。
例えば、若手が「この負荷計算、こういう方法でやってみたんですが…」と、明らかに基準から外れた方法を提案してきたとします。
このとき、「それは違う」「なんでそう考えたの?」と否定から入ってしまうと、若手は「間違ったことを言って恥ずかしい」と感じ、次から報告を躊躇するようになります。
私が実践しているのは、まず肯定するアプローチです。
私: 「なるほど、そういう考え方もあるね。その方法を選んだ理由を教えてくれる?」
若手: 「台数を減らせると思ったんです」
私: 「コスト面を考えたんだね、それはとても大事な視点だよ。実は、この部分には決められたルールがあって、こういう方法が必要なんだ。でも、コスを考える姿勢は素晴らしいから、その視点は別の部分で活かせるといいね」
このように、「それもいいね」と一度受け止めてから、正しい方向へ導くことを心がけています。
重要なのは、若手の「考えたこと」そのものを否定しないことです。たとえ答えが間違っていても、「考えようとした姿勢」は評価に値します。この積み重ねが、「何を言っても大丈夫」という心理的安全性を生み出します。
「沈黙」も大切なコミュニケーション
若手が何かを報告しようとして、言葉に詰まることがあります。「えーと、その、なんというか…」と、うまく説明できずにいる。
そんなとき、私は急かさず、静かに待つようにしています。相手が言葉を整理する時間を与えます。
焦って言葉を引き出そうとすると、若手はさらに混乱してしまいます。沈黙を恐れず、相手のペースを尊重することも、報連相しやすい環境を作る大切な要素だと感じています。
なぜ現場が緊張してしまうのか
私もよくありますが、つい感情的に厳しくなってしまうことがあります。それはなぜでしょうか。振り返ってみると、いくつかの理由が見えてきました。
責任とスケジュールのプレッシャー
プロジェクトの終盤で、スケジュールが厳しいとき。「ミス=自分の責任」というプレッシャーを感じています。
例えば、設計図の納期が迫っているときに、若手が作成した計算書に大きな見落としが見つかったとします。その瞬間、頭の中では「この修正に何時間かかる?」「他の図面への影響は?」「施工業者への説明はどうする?」と、一気に問題が膨らんでいきます。
本来なら冷静に「どこまで進んでいて、何が分からなかったのか」と聞くべきなのに、「なんでこうなる前に相談しなかったのか」と、感情的な言葉が先に出てしまう。後から「言い過ぎたな」と反省するのですが、その瞬間は余裕がなくなっているんです。
これは、自身が「精神的に余裕がない」というサインだと思います。プレッシャーが高まるほど、人は防衛的になり、言葉がきつくなってしまう。これは、先輩自身も苦しんでいる状態なんですよね。
「教える」ことの難しさ
長年の経験で身についた知識やコツは、意外と「言葉で説明するのが難しい」ものです。
私の例でお話しすると、電気設備の負荷計算をするとき、私は経験から「このビルなら照明負荷はこれくらい、コンセント負荷はこの程度」と、ほぼ自動的に判断できるようになっています。でも、「なぜそう判断したか」を言葉にしようとすると、実は説明が難しい。
若手に「どうやって算定したの?」と聞かれて、「えーと、まず建物用途を見て、それから平均的な負荷密度を参考にして…いや、でも階高も考慮して…」と説明しているうちに、自分でも混乱してくることがあります。
その結果、「とにかく、このやり方で覚えておいて」と、理由を省略した指示になってしまう。若手は「なぜそうするのか」が分からないまま作業するので、応用が効かず、次も同じようなミスをする。すると、「前も言ったよね?」と、また厳しい言葉が出てしまう。
「これは常識だと思っていた」ということが、若手には全く伝わっていなかった。そんなすれ違いが、お互いのストレスを生んでいるんです。教える側も、実は「どう教えたらいいか」に悩んでいるケースが多いのではないでしょうか。
「相談のタイミング」の難しさ
若手は「忙しそうな先輩に、いつ声をかけたらいいんだろう」と迷うことが多いようです。
以前、若手社員に「なぜ早く相談しなかったの?」と聞いたことがあります。彼は「先輩が打ち合わせから帰ってきて、すぐにパソコンに向かっていたので、忙しそうだと思って…。それで、自分でなんとか解決しようと思っているうちに、時間が経ってしまいました」と答えました。
若手から見ると、先輩は常に忙しそうに見える。電話が鳴り、メールが届き、設計図面を広げている。「今、話しかけていいのかな」「こんな基本的なこと聞いたら、呆れられるかな」という遠慮が、報告を遅らせてしまうんです。
そして、問題が大きくなってから発覚すると、「もっと早く言ってほしかった」となってしまう。でも、冷静に考えれば、「いつ相談すればいいか」「どの段階で報告すべきか」を明確に伝えていなかった、先輩側の課題でもあるんです。
この「待ちの姿勢」が、お互いの不安と不信感を少しずつ積み重ねていき、ある日突然、感情的な対立として表面化する。これが、現場の人間関係を難しくしている大きな要因だと感じています。
私が実践している、スムーズな任せ方
この経験から、私は「お互いが安心できる仕組み」を意識的に作るようにしました。試行錯誤の中で見つけた方法を、具体的にご紹介します。
1. 「ベースを固める」認識の共有
仕事を頼むとき、私はいきなり全体像を説明せず、段階的に理解を深めていくアプローチを取っています。
最初のステップ:基礎の確認
例えば、新しい案件で電源設備の設計を任せるとき、まず「このビルの用途は何だっけ?」「主な電気負荷にはどんなものがある?」といった基本的な質問から始めます。
若手が「オフィスビルなので、照明とOA機器が主要負荷です」と答えたら、「そうだね。じゃあ、具体的にどんな照明器具が想定される?」とさらに深掘りします。このやり取りで、若手がどこまで理解しているか、どこでつまずきそうかが見えてきます。
部分的な実践とフィードバック
理解度が確認できたら、いきなり全体を任せるのではなく、一部分だけやってもらいます。
「じゃあ、まず1フロア分の照明負荷計算をやってみよう。計算式と考え方を整理して、明日の午前中に見せてね」という具合です。
翌日、その計算書を見ながら、「この部分の考え方はいいね。ただ、ここの台数はこういう理由でこうするといいよ」と、具体的なフィードバックをします。
徐々に範囲を広げる
1フロアができたら、次は「じゃあ、他のフロアもやってみよう。同じ考え方でいけるかな?」と範囲を広げていきます。このとき、若手が自分で応用できる部分と、まだサポートが必要な部分が明確になります。
このステップを踏むことで得られる効果:
-
若手は「何が分かっていないか」を自覚できる
-
先輩は教えるべきポイントを絞れる
-
失敗しても影響範囲が限定的
-
お互いの認識のズレを早期に発見できる
最初は時間がかかるように感じますが、結果的には大きな手戻りを防げるので、全体として効率的なんです。
2. ミスの報告を受けたときの心がけ
もし若手がミスを報告してきたら、私が一番大切にしているのは**「ミスの背景を理解すること」**です。
まず報告を歓迎する
最初に「気づいて教えてくれてよかった」と、報告してくれたことを評価します。ミスを隠さずに報告する勇気は、本当に価値があることですから。
ミスに気づいたプロセスを聞く
ここからが重要なポイントです。私は必ず「どうやってこのミスに気づいたの?」と尋ねます。
例えば、若手が「幹線の電圧降下計算にミスがありました」と報告してきたとします。
私: 「なるほど。で、どうやってこのミスに気づいたの?」
若手: 「チェックリストで確認していたら、電圧降下が4.5%になっていて、基準の3%を超えていることに気づきました」
このやり取りで、若手が自分でミスを発見できる能力を持っていることが分かります。これは素晴らしいことです。
あるいは、こんな答えが返ってくることもあります。
若手: 「実は、別の先輩が図面を見たときに指摘してくれて気づきました」
この場合も、「そうか、気づかせてもらったんだね。指摘された時、どう思った?」と続けます。若手自身が、なぜ見落としたのか考えるきっかけを作るためです。
構造的な問題か、個人のエラーか見極める
次に、**「なぜそのミスが起きたのか」**を一緒に考えます。ここで私が注目するのは、これが「構造的な問題」なのか「個人のエラー」なのかという点です。
構造的な問題の例:
-
「計算式のテンプレートが古くて、最新の基準に対応していなかった」
-
「参照すべき資料がどこにあるか分からなかった」
-
「似たような図面番号が複数あって、どれが最新版か判断できなかった」
-
「途中で設計条件が変更されたが、その情報が共有されていなかった」
こういった問題は、若手個人の責任ではありません。仕組みや情報共有のプロセスに課題があるということです。
この場合、私は「これは君だけの問題じゃないね。みんなが同じミスをする可能性がある。じゃあ、どうすれば防げると思う?」と問いかけます。
例えば、「最新版の図面には『最新版』というスタンプを押すルールを作ろう」とか、「設計条件変更があったら、必ずチーム全体にメールで周知しよう」といった仕組みの改善につなげます。
個人のエラーの例:
-
「計算式は合っていたが、数字の入力ミスがあった」
-
「チェックリストを使わずに提出してしまった」
-
「作業に集中しすぎて、基準の確認を忘れていた」
個人のエラーの場合でも、「どうすれば次は防げると思う?」と、解決策を一緒に考えます。
若手: 「計算が終わったら、一度休憩してから見直す時間を取ればよかったと思います」
私: 「いいね。疲れた状態でチェックしても、ミスは見つけにくいからね。じゃあ、次からは作業時間を見積もるときに、見直しの時間も含めて計画しよう」
このように、ミスを「責任追及の場」ではなく、「学びと改善の機会」に変えることを意識しています。
「繰り返されるミス」への対応
同じ若手が同じようなミスを繰り返す場合は、もう少し踏み込んだ対話をします。
「このミス、以前にも同じようなことがあったよね。前回、どんな対策を立てたっけ?」と、過去の振り返りから始めます。
対策を立てていたのに実行できていない場合は、「その対策が実行しにくい理由があるのかな?」と、根本的な原因を探ります。
例えば、「チェックリストを使う」と決めたのに使っていない場合、「チェックリストが使いにくいのかな? どういうフォーマットなら使いやすい?」と、若手の意見を聞きます。
人によって作業スタイルは違うので、その人に合った方法を一緒に見つけることが大切です。
リカバリープランを一緒に作る
ミスの原因が分かったら、「じゃあ、このミスをリカバリーするために、今から何をすべきだろう?」と、冷静に解決策を一緒に考えます。
-
いつまでに修正が必要か
-
誰に報告や確認が必要か
-
他の図面への影響はないか
-
今後同じミスを防ぐために何をするか
これらを整理しながら、「修正は私も手伝うから、一緒にやろう」と伝えます。若手が一人で抱え込まないよう、サポート体制を明確にするんです。
このプロセスを続けると、若手は「問題が起きても、すぐに相談していいんだ」「ミスをしても、一緒に解決してくれる」と理解してくれます。このオープンなコミュニケーションこそが、組織全体の品質を守る力になると感じています。
3. チーム全体で支え合う雰囲気づくり
リーダーである私が常に若手の相談相手になるのは、実は理想的ではありません。なぜなら、私一人に依存する構造は、私が不在のときに業務が止まってしまうリスクがあるからです。
そこで私が意識しているのは、チーム全体で若手を育てる環境を作ることです。
あえて「自分がいない場面」を作る
チームに他のメンバーがいる場合、私は意図的に自分が席を外す時間を作ります。
例えば、若手が作業をしている日に、「午後は外出するから、分からないことがあったら〇〇さん(中堅社員)に聞いてね」と伝えておきます。
最初は若手も遠慮がちですが、中堅社員に質問することで、「リーダー以外にも相談できる人がいる」と気づきます。そして、中堅社員にとっても、人に教えることで自分の理解が深まり、成長の機会になるんです。
チーム全体で「相談しやすい空気」を作る
私が特に大切にしているのは、誰かが質問したときの周りの反応です。
若手が「すみません、この計算式の意味が分からないんですが…」と質問したとき、周りのメンバーが「それは前も説明したよね」といった反応をしてしまうと、若手は次から質問をためらうようになります。
そこで私は、チームミーティングで「質問は大歓迎。同じことを何度聞いても大丈夫」という価値観を繰り返し伝えています。そして、誰かが質問したときには、「いい質問だね」「実は私も昔、同じところで悩んだよ」といった肯定的な反応を、私が率先して示すようにしています。
リーダーが完璧でなくていい
私自身、分からないことがあれば「ちょっと確認させて」と素直に言うようにしています。リーダーが「知らないこと」を認める姿を見せることで、若手も「分からないことは恥ずかしいことじゃない」と学びます。
先日も、新しい基準について若手に質問されて、「その改正、まだ詳しく読んでないんだよね。一緒に確認しようか」と答えました。その場でウェブサイトを開いて、一緒に調べる。これも、チーム全体で学び合う文化を作る一つの方法だと思っています。
おわりに:一緒に成長できる現場を目指して
電気設備設計のリーダーとして、私も試行錯誤の連続です。でも、「上手に任せる」ことは、若手を育てるだけでなく、自分自身の負担も軽くしてくれることに気づきました。
もしあなたも若手育成について悩んでいるなら、できることから試してみてください。お互いに安心して働ける環境こそが、より良い設計を生み出す土台になるはずです。一緒に、次の世代が活躍できる現場を作っていきましょう。