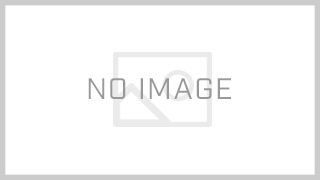🔍 電気設備理論クイズ 活用のすすめ
電気設備設計において、電気設備理論の正確な理解は安全・品質・効率のすべてに関わる重要な要素です。
本クイズは、設計実務に直結する条項を中心に構成された **「〇✕形式の確認問題」**です。
日常業務の合間に取り組むだけで、自然と知識の定着と再確認ができる内容となっています。
設計の現場でありがちな「うろ覚え」を減らし、確信を持って判断できる力を養うために、
ぜひこのクイズをご活用ください。
📘 電気設備理論クイズ
次の文が正しいかどうかを「〇(正しい)」「✕(誤り)」で答えてください。
短絡電流は、電源側変圧器のインピーダンスが小さいほど大きく、変圧器から短絡点までのこう長が長いほど小さい。
📖【一般理論】
▶ 〇(正しい)
高圧真空遮断器は、真空中のアーク拡散により消弧し、火災、爆発の恐れがなく、真空漏れの検出も容易である。一方遮断時には異常電圧を発生するおそれがある。
📖【一般理論】
▶ 〇(正しい)
高圧交流負荷開閉器は、通常状態において負荷電流・励磁電流・充電電流を開閉できる。一方、断路器は無負荷状態で設備を回路から切り離すために用いられる。
📖【機器機能】
▶ 〇(正しい)
責任分界点には地絡継電装置を取り付け、不要動作の恐れがある時は地絡方向継電器(DGR、ZCT、ZPD)とする。
▶ 〇(正しい)
高圧引込電線の布設を地中管路による場合は、管路式、暗きょ式、直接埋設式のいずれかとする。
▶ 〇(正しい)
引込線の太さは、最大負荷電流以上の許容電流のものとし、短時間許容電流は考慮しなくてもよい。受電点の短絡電流が8kAの場合はCVT22㎟以上とする。
▶ ✕(誤り)
❌ 誤答ポイント:「短時間許容電流は考慮しない」「CVT22㎟以上」→ 正しくは短時間許容電流も考慮し、8kA→CVT38㎟以上
コンクリート柱の太さを表す数値の1番目「12」は長さ(m)、2番目「19」は末口径(cm)、3番目はひび割れ試験荷重(kN)を示す。
▶ 〇(正しい)
PASの制御装置は、過電流ロック機能と過電流蓄勢トリップ付地絡トリップ形(SOG)とする。制御装置の100V電源は、PASにVTを外付けする。
▶ ✕(誤り)
❌ 誤答ポイント:「VTを外付け」→ 正しくはPASにVTを内蔵する
地中管路の種類は鋼管、コンクリート管、合成樹脂管、陶管のいずれかとし、管径はケーブル外径の1.2倍以上とする。また高圧ケーブルの曲げ半径は、単心で外径の8倍、多心で6倍とする。
▶ ✕(誤り)
❌ 誤答ポイント:「管径1.2倍」「単心8倍」→ 正しくは管径1.5倍以上、単心10倍、多心8倍
避雷器(LA)はPASに内蔵し、その接地抵抗値は10Ω以下、接地線の太さは14㎟以上、長さは15m以内を目安とする。
▶ 〇(正しい)
高圧引込柱は原則としてA種コンクリート柱とし、太さは引込柱で12-19-50、中間柱で12-19-35とする。
▶ 〇(正しい)
引留柱には、原則として支線を設ける。
▶ 〇(正しい)
VCT(電力需給用計器用変成器)、Wh(電力量計〈取引用〉)は、電力会社が機器の手配・取付工事を行う。
▶ 〇(正しい)
変圧器の損失は、全負荷運転から1/2負荷運転になったとき、鉄損は変わらず、銅損は1/2になる。
📖【P62(変圧器)】
▶ ✕(誤り)
❌ 誤答ポイント:「銅損は1/2」→ 正しくは1/4(電流の2乗に比例)
送電系統におけるフェランチ現象は、電線路のこう長が長いほど起こりやすい。また、地中ケーブルより架空電線路の方が起こりやすい。
📖【一般現象】
▶ ✕(誤り)
❌ 誤答ポイント:「架空電線路の方が起こりやすい」→ 正しくは地中ケーブルの方が起こりやすい
人間の目に光として感じる波長の範囲は、約380~780nmである。明るい場所では555nm(黄緑)が最も明るく感じられ、暗い場所では510nmが最も明るく感じられる。
📖【光学基礎】
▶ 〇(正しい)
暗いところから明るい場所に出る際には目が慣れるまでに時間がかかるが、明るい場所から暗い場所に入る場合は時間はかからない。これを暗順応という。
📖【視覚生理】
▶ ✕(誤り)
❌ 誤答ポイント:「明→暗は時間がかからない」→ 正しくは暗順応は明→暗で時間がかかる
演色性とは、太陽(自然光)を基準とした色の見え方のことをいい、パソコン画面などの極端に高い輝度が不快感を与える現象をグレアという。
📖【照明工学】
▶ 〇(正しい)
点光源から距離 r(m)離れて直角に受ける面上の点Pの照度E(lx)は、点光源の光度I(cd)に比例し、距離の2乗に逆比例する。
📖【逆二乗の法則】
▶ 〇(正しい)
光束法による平均照度の式は E = F・N・U・M/A、室指数RIは RI = X・Y/H(X+Y)で算出される。
📖【照度計算式】
▶ 〇(正しい)
タスク・アンビエント照明とは、作業エリアのみを強調照明し、周囲空間の照明は基本的に設けない方式である。
📖【照明方式】
▶ ✕(誤り)
❌ 誤答ポイント:「周囲空間には照明を設けない」→ 正しくは作業部に局部照明+周辺部に全般照明
照明器具の光源すべてから出る光束のうち、被照面に届く光束の割合を照明率といい、時間の経過に伴う照度低下を補正する係数を保守率という。
▶ 〇(正しい)
LED照明器具の一般的な使用条件は、電源電圧:定格電圧±6%、周囲温度5~35℃、相対湿度85%以下である。
📖【製品仕様】
▶ 〇(正しい)
照明エネルギー消費係数(CEC/L)は、年間照明消費エネルギー量を仮想照明消費エネルギー量で割った値で、数値が大きいほど省エネ効果が高い。
📖【省エネルギー評価】
▶ ✕(誤り)
❌ 誤答ポイント:「数値が大きいほど省エネ」→ 正しくは小さいほど省エネ効果が高い
建物の用途によって異なるが、照明設備が使用する電力量は、全体の設備電気使用量の**約30%**程度である。
📖【建築設備エネルギー統計】
▶ 〇(正しい)
直列リアクトルは主に奇数次の高調波障害対策に用いられ、放電コイルは残留電荷を放電する装置として使用される。
📖【P114/高調波対策】
▶ 〇(正しい)
CB形受電設備に避雷器を取り付ける場合は、主遮断装置の負荷側の直後から分岐し、避雷器専用の断路器を設ける。
📖【P117】
▶ ✕(誤り)
❌ 誤答ポイント:「負荷側」→ 正しくは電源側
地中引込線を管路式又は直接埋設式により施設する場合は、ケーブルの埋設箇所の表示を行う。ただし、地中電線路の長さが15m以下のものにあってはこの限りではない。
▶ 〇(正しい)
地中電線相互の離隔距離は、低圧地中電線と高圧地中線では15cm、低圧または高圧地中電線と特別高圧地中線では30cmとする。
▶ 〇(正しい)
高圧受電設備の保安上の責任分界点は、電力会社構外に設けるのが原則である。区分開閉器を施設し、断路器を使用する。
▶ ✕(誤り)
❌ 誤答ポイント:「構外」「断路器使用」→ 正しくは構内に設け、区分開閉器には高圧交流負荷開閉器を使用
区分開閉器の選定では、PASに流れる最大負荷電流に対応し、短絡電流への耐力とインパルス耐電圧を満足することが必要である。
▶ 〇(正しい)
PASの選定は、負荷電流以上の定格電流と短絡電流に耐える定格電流であること。受電点の短絡電流が8kAを超える場合は、300A以上の開閉器を選定する。
▶ 〇(正しい)
高圧引込設備の単線結線図には、電源の相数・線数、受電電圧、周波数を明記する必要がある。
▶ 〇(正しい)
ハンドホール・マンホールは、直線区間においてハンドホールは100mごと、マンホールは200mごとを目安に1箇所設ける。
▶ ✕(誤り)
❌ 誤答ポイント:「100m・200m」→ 正しくはハンドホール50m・マンホール100m
SOG制御装置とは、「Storage(蓄勢)Over current(過電流)Ground(地絡)」の略で、過負荷や短絡時に瞬時動作し、PASを開放する装置である。
▶ ✕(誤り)
❌ 誤答ポイント:「短絡時に瞬時動作」→ 正しくは短絡時は動作せず、地絡時に瞬時開放/無電圧時に蓄電で開放
ハンドホール・マンホールのふたの荷重区分には、軽荷重(2トン以下)、中荷重(4, 6, 8トン以下)、重荷重(20, 25トン以下)がある。
▶ 〇(正しい)
引込みに使用する耐火ケーブルは、非常電源専用受電設備で用いる。官公庁工事では、燃焼時に有毒ガスを発生するVVFケーブルを優先して使用する。
▶ ✕(誤り)
❌ 誤答ポイント:「VVFケーブルを優先」→ 正しくはエコ電線(EM電線)を使用
JIS C 4620「キュービクル式受電設備」において、受け渡し試験時には構造試験、動作試験、耐電圧試験を実施する。
📖【JIS C 4620】
▶ 〇(正しい)
高圧ケーブルの絶縁体には、その内外に半導電層を設けて電界を均一化するとともに、外側には銅テープによる遮へい層を設けて接地することで外部への電界の影響を防ぐ。
📖【高圧ケーブル構造】
▶ 〇(正しい)
ヒューズ定格の2〜3倍という過負荷電流域では遮断不能になるという限流ヒューズの課題を解決するのがLBSのストライカの機能であり、遮断性能の向上や欠相防止が図られる。
📖【P105】
▶ 〇(正しい)