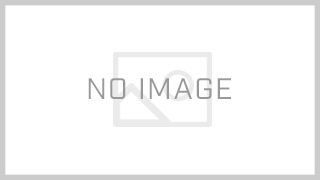屋内消火栓の設置基準
屋内消火栓の設置基準
🎯この章で学べること
ハリタ先生
ペン太くん、こんにちは!今回は、建物の安全を守る上でとても重要な「屋内消火栓設備」の設置基準について学んでいこう。
ペン太
はい!消火器は知ってるけど、消火栓はなんだか難しそうです。しっかり頑張ります!
この章の学習目標
- ✓屋内消火栓の設置が必要になる条件を理解する。
- ✓「延べ面積」と「特定の階」の条件を区別できるようになる。
- ✓防火対象物ごとの基準を把握する。
ℹ️設置基準の基本的な考え方
ハリタ先生
屋内消火栓の設置基準は、主に**防火対象物の用途と規模(延べ面積)**、そして**特定の階の面積**で決まるんだ。まずはこの基本を頭に入れよう。
設置基準の2つの柱
屋内消火栓の設置基準は、主に**防火対象物の用途と規模(延べ面積)**、そして**特定の階の面積**で決まるよ。
これらの条件は、火災が発生した際のリスクを考慮して定められているんだ。延べ面積が大きくなるほど、また地下や窓がない階など、危険度が高い場所には早期の消火活動ができる設備が必要になるからね。
ペン太
用途や建物の形によって、基準が変わるんですね!なるほど!
📝設置基準の表の見方
ハリタ先生
設置基準の表に書いてあるカッコ内の数字、あれには特別な意味があるんだ。その見方について解説しよう。
倍読み規定(緩和措置)とは?
防火対象物の**主要構造部**が**耐火構造**や**準耐火構造**の場合、設置基準の緩和が認められることがある。これを**倍読み規定**と呼ぶよ。
耐火・準耐火構造
→ 燃えにくい構造
基準が緩和される
その他構造(木造など)
→ 燃えやすい構造
基準が厳しくなる
この規定は、「燃えにくい構造の建物は、火災が起きても延焼が遅れるため、消火栓の設置基準を少し緩やかにしても良い」という考えに基づいているんだ。
例えば、添付の表にある通り、劇場・映画館の延べ面積基準は「500㎡」だけど、耐火構造の場合は「(1000)㎡」や「{1500}㎡」に緩和される。
| 令別表第一 | 防火対象物の種別 | 一般条件 | |
|---|---|---|---|
| 延べ面積㎡ | 床面積㎡ | ||
| (1) | イ 劇場、映画館 | 500 (1000){1500} |
100 (200){300} |
| (2) | 病院、診療所 | 700 (1400){2100} |
150 (300){450} |
| (12) | 工場、倉庫 | 700 (1400){2100} |
150 (300){450} |
( )と { } の違いについて
表に記載されているカッコ内の数値は、建物の構造によって異なる緩和規定を意味するよ。
**( )内の数値:** 主要構造部が**準耐火構造**(または同等の性能)で、かつ内装制限が施されている建物に適用される。
**{ }内の数値:** 主要構造部が**耐火構造**で、かつ内装制限が施されている建物に適用される。
つまり、より火災に強い「耐火構造」の建物は、さらに大幅な緩和が受けられるんだね。
主要構造部とは?
**主要構造部**とは、建物の骨格を形成する**柱、床、壁、はり、屋根、階段**などのことを指すよ。
これらの部分が耐火構造や準耐火構造でできている場合に、上記のような緩和規定が適用されるんだ。
ペン太
建物の材質によって、同じ面積でもルールが変わるんですね!これは大事なポイントだ!
📐延べ面積と特定の階の基準
ハリタ先生
さて、具体的な数字を見ていこう。防火対象物には、その用途によって設置基準となる延べ面積が決められているんだ。
1. 延べ面積による設置基準
防火対象物の用途に応じて、延べ面積が以下のいずれかを超えると屋内消火栓の設置が必要になるよ。
500㎡以上
(1)項イ:劇場、映画館など
700㎡以上または1000㎡以上
(2)項〜(16)項:病院、工場、倉庫など
2. 特定の階による設置基準
延べ面積が基準未満でも、以下の階に該当し、かつその床面積が基準以上だと設置が必要になるんだ。
特定の階の設置条件
**地階、無窓階、4階以上の階**は、避難や消防活動が難しいため、特に厳しい基準が設けられているよ。
地階
⬇️
避難が困難
地上への経路が限られる
無窓階
🧱
消防活動が困難
外部からの進入・放水ができない
4階以上の階
🏢
避難・救助が困難
はしご車が届きにくい
3. 設置基準の特例
指定された場所にスプリンクラー設備や動力消防ポンプ設備を設置することで、屋内消火栓の基準が緩和される場合があるよ。
ただし、これらの設備を設置しても、延べ面積による設置基準が完全に免除されるわけではないので注意が必要だ。
ペン太
地階や無窓階は、地上と違って逃げ道が少ないから、特に注意が必要なんですね!
👷設置場所と注意すべきポイント
ハリタ先生
設置基準を満たしていても、正しい場所に設置しないと意味がない。設置場所に関する重要なポイントも確認しておこう。
消火栓の設置場所
消火栓から防火対象物の各部分までの**水平距離**が**25m以内**になるように設置する。
誰もがすぐに使えるよう、操作が困難な場所(柱の裏など)には設置しない。
消火栓の格納箱には、**「消火栓」**と表示された標識を設置する。
消火栓の前には、消火活動の妨げになるような物を置かない。
寒冷地などでは、水が凍結しないように保温措置を講じる。
遠くからでも消火栓の位置がわかるように、設置場所に表示灯を設ける。
ホースの長さは、消火栓から防火対象物の各部分まで有効に放水できる長さにする。
ペン太
消火栓はただ設置すればいいってわけじゃなくて、いつでも使えるようにしておくことが大事なんですね!
🚶歩行距離と水平距離のちがい
ハリタ先生
さっき「歩行距離」という言葉が出てきたけど、これと似た「水平距離」という言葉があるんだ。この二つをきちんと区別しよう。
歩行距離とは?
**歩行距離**とは、実際に人が歩く経路に沿って測った距離のことだよ。
水平距離とは?
**水平距離**は、建物の構造などを無視して、地図上で測るような直線距離のことだよ。
- 歩行距離:通路、階段、扉などを通る、実際の道のり。
- 水平距離:測る地点から対象物までを直線で結んだ距離。
ペン太
なるほど!障害物を避けて進む道のりが「歩行距離」なんですね!
🔥耐火構造と準耐火構造の違い
ハリタ先生
今回は特別に、建物そのものの「燃えにくさ」に関する重要な知識を教えよう。建物の構造には、火災に強い**耐火構造**と**準耐火構造**があるんだ。
1. 耐火構造とは?
**耐火構造**とは、建築基準法で定められた**耐火性能**を持つ構造のことだよ。建物の倒壊や延焼を防ぐために、鉄筋コンクリートやレンガ、耐火被覆を施した鉄骨などが用いられる。
👉 **最長3時間**、火災に耐える性能を持っているよ。
2. 準耐火構造とは?
**準耐火構造**は、耐火構造よりも緩やかだけど、火災による延焼を抑制する**準耐火性能**を持つ構造だよ。主要構造部に不燃材料や準不燃材料が使われる。
👉 **最長1時間**、火災に耐える性能を持っているよ。
ペン太
耐火構造の方が、より長時間火災に耐えられるんですね!分かりやすいです!
🚧内装制限について
ハリタ先生
建物の構造だけでなく、内装にも火災の広がりを抑えるためのルールがあるんだ。これが**内装制限**だよ。
内装制限の目的と対象
内装制限は、火災時に内装材(壁紙など)が激しく燃えて**有毒ガス**を発生させたり、延焼を促進したりするのを防ぐための規制だよ。
- 対象は主に**壁**と**天井**。
- **床**は内装制限の対象外。
- **難燃材**、**準不燃材**、**不燃材**といった燃えにくい材料の使用が義務付けられている。
建築基準法と消防法の違い
内装制限には、**建築基準法**と**消防法**でそれぞれ異なる規定があるから注意が必要だよ。
これは、火災の早期段階で煙が充満しやすい建物の下部にも、燃えにくい材料を使うことで避難時間を確保しようという目的があるんだね。
ペン太
壁紙や内装材まで細かく決まってるなんて知りませんでした!法律によっても基準が違うんですね。
🆚1号消火栓と2号消火栓の主な違い
ハリタ先生
屋内消火栓には、主に**1号消火栓**と**2号消火栓**の2種類があるんだ。それぞれの違いをしっかり押さえておこう!
消火能力と操作性で使い分け
**1号消火栓**は放水性能が高く、短時間に大量の水を放水できるため、大規模な火災の消火活動を想定しているよ。しかし、ホースが重く、操作に2名以上を必要とすることが多いんだ。
一方、**2号消火栓**は1号消火栓に比べると放水性能は劣るものの、操作が簡易で一人でも消火活動を実践しやすい構造になっているのが大きな特徴だ。一般の人が初期消火に使用することを想定しているんだね。
また、2号消火栓の利便性に近く、かつ1号消火栓の消火能力を保持する**「易操作性1号消火栓」**と呼ばれるタイプもあるよ。これは一人で操作できるように改良された1号消火栓のことだ。
設置対象と性能の比較表
両者は、建物の種類や規模、そして性能によって設置基準が異なるよ。
| 区分 | 1号消火栓(令11-3-1) | 2号消火栓(令11-3-2) | ||
|---|---|---|---|---|
| 易操作性以外 | 易操作性 | 広範囲型以外 | 広範囲型 | |
| 防火対象物の区分 | a. (12)項イ(工場)、(14)項(倉庫)の防火対象物 b. 令別表第1に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物(可燃性液体類を除く。)を危令別表4で定める数量の750倍以上を貯蔵し又は取り扱うもの c. a及びb以外の防火対象物 |
左欄の a及びb以外の防火対象物 | ||
| 水平距離 | 25m以下 | 15m以下 | 25m以下 | |
| 放水圧力 | 0.17MPa〜0.7MPa | 0.25MPa〜0.7MPa | 0.17MPa〜0.7MPa | |
| 放水量 | 130ℓ/min以上 | 60ℓ/min以上 | 80ℓ/min以上 | |
| 非常電源 |
非常電源専用受電設備(特定防火対象物で延べ面積1,000㎡以上のものを除く。) 自家発電設備 蓄電池設備 燃料電池設備 |
|||
ペン太
消火栓って、時代に合わせて進化しているんですね!
📦パッケージ型消火設備(屋内消火栓の代替設備)
ハリタ先生
屋内消火栓設備の設置が難しい場合、その代替として**パッケージ型消火設備**が認められることがあるんだ。特に中小規模の建物向けに作られた設備だね。
パッケージ型消火設備とは?
この設備は、ノズル、ホース、リールまたはホース架、消火薬剤貯蔵容器、起動装置、加圧用ガス容器などが**一つの格納箱に収められている**移動式消火設備だよ。
**主なメリット**
配管・非常電源が不要!
設置にかかる工事の手間とコストを大幅に削減できるよ。
省スペース
コンパクトにまとまっているため、場所を取らないよ。
移動式
必要に応じて移動させることができるよ。
なお、パッケージ型消火設備には「I型」と「II型」の規定があるが、現在のところ**「I型」のみ**が製造されているようだ。
設置に関する注意点
パッケージ型消火設備は、以下の場所には設置できないとされているんだ。
- 火災のとき著しく煙が充満するおそれのある場所
これは、「初期消火や避難を行う上で有効な、外気に直接開放された開口部を有しない場所」を指すよ。つまり、煙がこもりやすく避難が難しい場所では使えないんだ。
ペン太
屋内消火栓の代わりになる設備もあるんですね!建物の種類に合わせて最適なものを選ぶことが大切だ!
❓ペン太の質問コーナー
ペン太
先生、危険物施設や指定可燃物にも消火栓は必要ですか?水に反応して危険なものもありますよね?
ハリタ先生
いい質問だね。一部の危険物(例えば禁水性物質)は水をかけると危険なので、屋内消火栓の設置基準が**適用外**になるよ。しかし、水で消火できる危険物や指定可燃物については、消防法の基準に従って設置が必要になるんだ。
詳しくは専門家や消防機関に確認する必要があるけど、基本的には水の危険性がある場合は除外されると覚えておこう。
📖まとめ
この章では、屋内消火栓の設置基準について、さまざまな角度から学習したね。
今日学んだことのポイント
- **設置基準の基本:**防火対象物の**用途・延べ面積**と、**特定の階(地階・無窓階・4階以上)**の面積によって設置が必要になる。
- **倍読み規定:**建物の主要構造部が**耐火構造**や**準耐火構造**の場合、基準が緩和されることがある。
- **1号と2号消火栓:****1号消火栓**は大規模火災向けで放水性能が高いが、操作に2名以上を要する。**2号消火栓**は初期消火向けで、一人でも操作しやすい構造になっている。
- **パッケージ型消火設備:**配管や非常電源が不要で、簡易に設置できる消火栓設備の代替となるものもある。
ペン太
たくさん大事なことを学べました!これで、屋内消火栓のことがばっちりです!
ハリタ先生
その調子だ、ペン太くん!これからも一緒に、建物の安全について学んでいこう!
建物の安全を守る第一歩!屋内消火栓の設置基準を徹底解説
こんにちは!建物の安全を守るための設備、屋内消火栓についてご存知でしょうか? 火災が発生した際に、初期消火に非常に重要な役割を果たす屋内消火栓ですが、どんな建物にも設置されているわけではありません。 今回は、屋内消火栓の設置が必要となる条件や、その種類について、分かりやすく解説していきます。
1. 設置基準の基本的な考え方
屋内消火栓の設置基準は、主に防火対象物の種類と建物の規模によって決まります。 特に、不特定多数の人が出入りする劇場や病院、火災の際に被害が拡大しやすい工場や倉庫などは、火災のリスクが高いため、より厳しい基準が設けられています。 また、建物の延べ面積が大きくなるほど、火災時の消火活動が困難になるため、設置義務の対象となります。
2. 建物の構造による基準の緩和(倍読み規定)
建物の主要構造部が耐火構造や準耐火構造である場合、火災の進行が遅れるため、設置基準が緩和されることがあります。
- 準耐火構造: 火災に最長1時間耐える性能を持ち、基準が2倍に緩和されます。
- 耐火構造: 火災に最長3時間耐える性能を持ち、基準が3倍に緩和されます。
これにより、燃えにくい建物ほど、設置基準となる面積のハードルが上がる、ということになります。
3. 1号消火栓と2号消火栓の違い
屋内消火栓には、主に以下の2つの種類があります。
- 1号消火栓: 大規模な火災の消火を目的とし、放水性能が高い反面、操作には2名以上を要することが多いタイプです。
- 2号消火栓: 初期消火を目的とし、比較的放水性能は劣りますが、操作が簡易で一人でも使いやすいように設計されています。
4. 設置場所のルール
屋内消火栓は、ただ設置すれば良いというわけではありません。いざという時に誰もが確実に使えるよう、以下のルールが定められています。
- 水平距離: 消火栓から防火対象物の各部分までの水平距離が25m以下となるように設置する必要があります。これは、ホースを伸ばして消火できる範囲を確保するためです。
- 操作性: 誰でも簡単に操作できるよう、設置場所に障害物がないことや、標識・表示灯を設けることが義務付けられています。
まとめ
この記事では、屋内消火栓の設置基準について解説しました。 建物の種類や規模、構造によって、設置義務や基準が細かく定められていることがお分かりいただけたかと思います。 私たちの身近にある屋内消火栓は、建物の安全を守る上で欠かせない存在です。ぜひ、お近くの建物の屋内消火栓にも注目してみてください