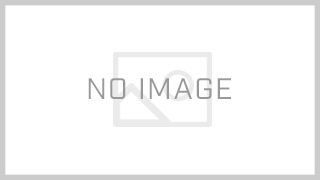非常電源専用受電設備
非常電源専用受電設備
🎯この章で学べること
ハリタ先生
今日は、建物の非常電源として検討される「専用受電設備」について学んでいこう!これは、自家発電機や蓄電池を使わずに、電力会社からの電力をそのまま非常電源として利用するんだ。
ペン太
発電機とかがなくても、非常時に電気が使えるってことですか?すごいですね!
この章の学習目標
- ✓専用受電設備とは何かを説明できる。
- ✓非常用発電機とのコスト面での違いを理解できる。
- ✓専用受電設備のメリットとデメリットを比較検討できる。
ℹ️専用受電設備のメリットとデメリット
ハリタ先生
専用受電設備には、コストやスペースの面で大きなメリットがあるんだ。その一方で、停電時にはリスクもあることを理解しておく必要があるよ。
専用受電設備のポイント
専用受電設備は、自家発電機や蓄電池を設置しないため、**イニシャルコスト**や**ランニングコスト**を大幅に削減できる点が大きな利点です。また、燃料の確保や保管スペースも不要になります。
メリット
→ **低コスト化** (設置・維持費)
→ **省スペース化** (燃料・機器不要)
デメリット
→ **停電リスク** (電力会社の供給が止まると機能しない)
→ **保安電源の機能なし** (消防用設備以外に使えない)
ペン太
なるほど!初期費用が抑えられるのは魅力的だけど、災害時のことを考えると少し不安ですね。
📝BCPと非常用電源の比較
ハリタ先生
非常用発電機や蓄電池の役割が再注目されているんだ。専用受電設備と、これらの設備を比較してみよう。
非常用電源の比較表
| 項目 | 非常電源専用受電設備 | 非常用発電機・蓄電池 |
|---|---|---|
| コスト | 初期費用・維持費が安い | 初期費用・維持費が高い |
| 停電時のリスク | 電力会社の供給に依存する | 独立した電源でリスクが低い |
| BCPへの貢献 | 限定的(消防設備のみ) | 高い(保安電源として活用可能) |
ペン太
なるほど!BCPを重視するなら、発電機が必要になるんですね。目的によって最適な設備が違うってことか!
🚨適用可能な消防用設備と面積制限
ハリタ先生
専用受電設備が使えるのは、消防用設備の中でも限られたものだけなんだ。適用できる面積にも注意が必要だよ。
適用可能な消防用設備
- 🧯 屋内消火栓設備
- 💧 スプリンクラー設備
- 💨 水噴霧消火設備
- 🧼 泡消火設備
- 🚰 屋外消火栓設備
- 🔔 自動火災報知設備
- 📢 非常警報設備
- 🌬️ 排煙設備
- 🚒 連結送水管の加圧送水装置
- 🔌 非常コンセント設備
- 📡 無線通信補助設備
📏面積制限に注意!
非常電源専用受電設備は、大規模な建物には適用できません。以下の制限があります。
特定防火対象物の場合
床面積が**1,000㎡以上**の建物には適用できません。
「16項イ」の防火対象物の場合
特定用途となる部分の床面積が**1,000㎡以上**となる場合は適用不可です。
ペン太
使える設備や建物の大きさにもルールがあるんですね。事前にしっかり確認しないと、後で大変なことになりそう…!
🚧設置基準
ハリタ先生
専用受電設備には、安全に運用するための設置基準があるんだ。設置場所や構造について、しっかり見ていこう。
基本原則と回路の扱い
専用受電設備は、**点検が容易**で、かつ**火災の被害を受けない場所**に設置することが原則です。また、他の電気回路の遮断器や開閉器によって回路が遮断されないこと、専用の開閉器には**「消防用設備等」であることを表示**することなどが定められています。
高圧・特別高圧受電の場合
高圧や特別高圧で受電する場合でも、専用受電設備の採用が可能です。
- 専用室を設ける場合:不燃材料で造られた壁・床・天井で区画し、窓や出入口に防火戸を設けた専用室に設置します。
- 専用室を設けない場合:建築物から3m以上離隔するか、主要構造部を耐火構造とした建築物の屋上(ペントハウスなどから3m以上離隔が必要)に設置します。
離隔が確保できない場合は、建築物の外壁や仕上げ面を不燃材料とし、開口部には防火戸を設けることで対応可能です。また、これらの対応が難しい場合は、キュービクル側の耐火性能を高めることで対応も可能です。**「キュービクル式非常電源専用受電の基準」に適合した認定キュービクル**を設ければ、建物側が不燃材料でなくても認可を受けられます。
ペン太
設置場所にも細かいルールがあるんですね。認定品と記載された図面をよく見ますね!
📋キュービクルの仕様
ハリタ先生
専用受電設備として使用できるキュービクルには、いくつかの基準があるんだ。「**告示第7号キュービクル**」と「**認定キュービクル**」の違いを見てみよう!
認定キュービクルと告示第7号キュービクルについて
非常電源専用受電設備のうち、高圧または特別高圧で受電する場合の基準として、**昭和50年、自治省(現総務省)消防庁告示第7号(改正告示第8号)「キュービクル式非常電源専用受電設備の基準」**が定められています。
これに準拠し、さらに厳しい基準を定めたものが「**認定キュービクル**」です。**専用受電設備に適用する際は、告示第7号キュービクル・認定キュービクルのどちらも使用可能です。**
告示第7号準拠品
製造メーカーによっては、所轄の消防署に個別に適用可否を判断してもらう必要があります。
認定キュービクル
日本電気協会が定めた厳しい基準に適合していることを証明する**銘板**が貼り付けられており、専用受電設備として適用できる場合がほとんどです。
注意:「推奨キュービクル」について
類似の規格として**「推奨キュービクル」**がありますが、これは品質向上を目的としたもので、専用受電設備としての基準を満たすものではありません。選定時には注意しましょう。
ハリタ先生
どちらのキュービクルを選ぶか、設計の際にはしっかり検討する必要があるね。選定のフローチャートを見てみよう!
専用受電設備 選定フロー
認定キュービクル
→ 銘板で確認可能
告示第7号準拠品
→ 所轄消防署との協議が必要
推奨キュービクル
→ 対象外
ペン太
フローチャートで考えると、手続きが全然違いますね!認定品の方がスムーズに進められそうだ!
ハリタ先生
認定を受けている分、選定する際は次に挙げる注意が必要だよ!
⚠️認定キュービクルの注意点
ハリタ先生
認定キュービクルは非常に便利だけど、一度設置した後にはいくつか注意すべき点があるんだ。特に増設や改造は慎重に行う必要があるよ。
新設時の注意点
認定キュービクルは、変圧器容量とブレーカー数がメーカーの規格と合わない場合、認定品としての製品が製作できない場合があるので計画する際は注意が必要です。
ハリタ先生
特に設計図に記載されている内容でも、メーカーの規格と合わないと製作できない場合があるんだ。だから、作図や見積の段階で、必ずメーカーに確認することが大切だよ!
増設・減設・改造時の注意点
認定キュービクルが現地に納入された後、何らかの理由で増設・減設または改造が必要になった場合は、**「注意ラベル」**にも記載されているように、以下の点に注意してください。
このキュービクル式非常電源専用受電設備は認定品であり、このキュービクルを増設・減設又は改造するときは、必ず当該キュービクルの製造業者と事前協議して下さい。
また、このキュービクルは消防法に基づく非常電源であり所轄消防署と事前協議を行い、改造内容や届出等の指示を受けて下さい。
一般社団法人 日本電気協会
【注意ラベル】
ペン太
一度設置したら終わりじゃなくて、何か変えるときもルールがあるんですね!ちゃんと確認しないと、せっかくの認定が台無しになっちゃうんだ!
🚧設置基準
ハリタ先生
専用受電設備には、安全に運用するための設置基準があるんだ。設置場所や構造について、しっかり見ていこう。
基本原則と回路の扱い
専用受電設備は、**点検が容易**で、かつ**火災の被害を受けない場所**に設置することが原則です。また、他の電気回路の遮断器や開閉器によって回路が遮断されないこと、専用の開閉器には**「消防用設備等」であることを表示**することなどが定められています。
高圧・特別高圧受電の場合
高圧や特別高圧で受電する場合でも、専用受電設備の採用が可能です。
- 専用室を設ける場合:不燃材料で造られた壁・床・天井で区画し、窓や出入口に防火戸を設けた専用室に設置します。
- 専用室を設けない場合:建築物から3m以上離隔するか、主要構造部を耐火構造とした建築物の屋上(ペントハウスなどから3m以上離隔が必要)に設置します。
離隔が確保できない場合は、建築物の外壁や仕上げ面を不燃材料とし、開口部には防火戸を設けることで対応可能です。また、これらの対応が難しい場合は、キュービクル側の耐火性能を高めることで対応も可能です。**「キュービクル式非常電源専用受電の基準」に適合した認定キュービクル**を設ければ、建物側が不燃材料でなくても認可を受けられます。
ペン太
設置場所にも細かいルールがあるんですね。認定品と記載された図面をよく見ますね!
🔌結線方法と保護協調
ハリタ先生
専用受電設備における電気回路の構成と、安全を確保するためのルールについて見ていこう。特に**MCCB**の容量選定には、変圧器が専用か共用かで異なるルールがあるので、しっかり覚えよう。
変圧器と回路の種類
💡専用変圧器
変圧器に非常電源回路のみが接続されている場合です。
⚠️共用変圧器
商用電源と非常電源回路が同じ変圧器に接続されている場合です。
MCCBの容量選定ルール
専用変圧器の場合
- MCCBが1台の場合:変圧器の定格電流の**1.5倍以下**とします。
- 非常回路が複数台の場合:MCCBの合計値は**1.5倍以下**とし、1台あたりは**1.0倍以下**とします。
共用変圧器の場合
**2.14倍ルール**が適用されます。
2.14倍ルール:配線用遮断器の定格電流の合計は、変圧器二次側定格電流の2.14倍以下にしなければなりません。
- 合計容量が2.14倍を超えた場合:一般回路に主幹MCCBを設け、主幹と非常回路の合計が2.14倍以下になるように調整します。
計算例で確認しよう
【前提条件】
変圧器:3φ3W 6.6kV/210V **100kVA**
変圧器二次側電流:**275A**
【計算】
変圧器定格電流 × **2.14** = 275A × 2.14 ≈ 589A…(1)
接続されているMCCBのトリップ値を合計する:
100AF 75AT
225AF 150AT
225AF 150AT
225AF 175AT
合計値: 75 + 150 + 150 + 175 = 550A…(2)
【判断】
(1) 589A > (2) 550A
このため、非常電源の要件を満たしていると判断できます。
ペン太
なるほど!実際に計算してみると、ルールの意味がよくわかります!
🔌引込ケーブルの耐火基準
ハリタ先生
最後に、引込ケーブルの耐火基準について学んでおこう。これも設計上の大事なポイントだ。
原則と例外の判断基準
原則:耐火ケーブルの使用
消防法や施行令に明確な規定がないため、多くの場合、受電点から**キュービクル一次側**までを耐火ケーブルとするよう指導されます。
例外:所轄消防との協議が必要
以下の条件を満たす場合、難燃性ケーブル(CVケーブルなど)が認められることがあります。
- 火災を受けるおそれがない場所に敷設される場合(地中埋設、屋外布設など)。
- 建築物内部の火災のおそれが少ない室(機械室やシャフトなど)のみを通過するように配線し、かつ金属管に収容する場合。
📋重要なポイント
どのような場合でも、最終的な判断は**所轄の消防署**との協議が不可欠です。設計の初期段階で必ず相談するようにしましょう。
ペン太
なるほど!法律だけでなく、実際に設計する場所や消防署との相談も大事なんですね。
📖まとめ
この章では、以下のポイントについて学習しました。
専用受電設備とは
自家発電機などを持たず、電力会社からの受電を非常電源とする方式。コスト面で優れている反面、停電時には機能しないリスクがある。
リスクとBCP
地震や落雷による停電リスクを考慮する場合、BCP(事業継続計画)の観点では非常用発電機などの独立した電源も検討すべきである。
適用可能な設備と制限
非常電源として認められる消防用設備は限られており、特定防火対象物では床面積1,000㎡未満という規模の制限がある。
キュービクルの仕様
「告示第7号キュービクル」と「認定キュービクル」の2つの規格がある。認定品は厳しい基準を満たし、手続きが比較的スムーズに進む。
設置基準
点検が容易で、火災の影響を受けない場所に設置することが原則。高圧受電では専用室の設置や建物からの離隔が求められる。
結線と保護協調
上位の受電用遮断器より先に回路が遮断されるよう保護協調を図る必要がある。共用変圧器には**2.14倍ルール**という合計定格電流の制限がある。
引込ケーブル
原則として耐火ケーブルが推奨されるが、設置場所や配線方法によっては難燃性ケーブルも認められる場合がある。所轄消防との協議が不可欠。
ペン太
災害時のリスクを理解した上で、用途に合わせて最適な電源を選ぶのが大事だとわかりました!
ハリタ先生
その通り!よく理解できたね!この知識を活かして、これからも頑張って学習しよう!
災害に備える!非常電源専用受電設備とは?
地震や台風など、いつ起こるか分からない災害。停電時にも消防設備が正常に作動するために、建物の非常電源は非常に重要です。この記事では、非常電源の一つである**「非常電源専用受電設備」**について、そのメリットやデメリット、選定時の注意点を分かりやすく解説します。
非常用発電機との違い
一般的に非常電源と聞いて思い浮かぶのは、自家発電機や蓄電池でしょう。これらは、万が一停電が発生した場合でも、建物内で独立して電力を供給できるため、BCP(事業継続計画)の観点からも非常に有効です。
一方、非常電源専用受電設備は、自家発電機などを設置せず、電力会社からの電力をそのまま非常電源として利用する仕組みです。
コストやスペースの面で優れている反面、大規模な停電時には機能しないリスクがあることを理解しておくことが重要です。
設置基準と選定のポイント
専用受電設備として認められるには、消防法で定められたいくつかの基準を満たす必要があります。
- 適用可能な設備: 連結送水管の加圧送水装置、排煙設備、非常コンセント設備など、利用できる消防用設備は限られています。
- 面積制限: 特定防火対象物の場合、床面積が1,000㎡以上の建物には適用できません。
- 設置場所: 点検が容易で、火災の影響を受けにくい場所に設置する必要があります。
また、専用受電設備に使用するキュービクルには、消防庁告示の「告示第7号キュービクル」と、日本電気協会が定めたより厳しい基準を持つ「認定キュービクル」があります。認定キュービクルには銘板が貼付されており、所轄の消防署との協議がスムーズに進むことが多いです。
非常電源の選定は、建物の規模や用途、そしてどのようなリスクに備えるかによって最適なものが異なります。災害に強い建物を建てるために、専門家と相談しながら最適な計画を立てることが大切です。