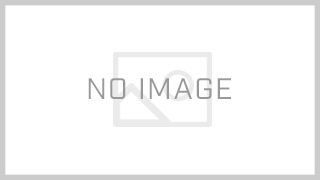始動電流を考慮すべし
動力負荷のブレーカーサイズ
選定方法について教えてほしい!
- 動力負荷のブレーカーサイズについて調べている方
- 選定したブレーカーサイズが大きいがあっているか心配な方
- ブレーカーサイズの選定方法
- 負荷に応じた正しいサイズの選定方法
- 選定の根拠資料について
ブレーカーサイズの簡易計算表

今回は、内線規程に記載されている下記内容についての解説します
3.電動機に電気を供給する分岐回路の過電流遮断器の選定は,次の各号による
こと。(解釈149)
① 過電流遮断器の定格電流は,当該電動機の定格電流の3倍(電動機の定格電流が50Aを超える場合は,2.75倍)に他の電気使用機械器具の定格電流の合計を加えた値以下で,かつ,電動機の始動電流により動作しない定格のものであること。ただし,電動機の過負荷保護装置との保護協調が適切であるときは,当該分岐回路に使用する電線の許容電流の2.5倍以下とすることができる。
まずは動力と電灯負荷の違いを認識しよう!
電気設備設計において、「動力」と「電灯負荷」は明確に区別して考える必要があります。
同じ“負荷”でも、その特性や開閉器の選定方法には大きな違いがあるのです。
💡 補足:始動電流とは?
始動電流とは、モーターなどを動かす瞬間に必要な大きな電流のことです。
通常、定格電流の3〜6倍程度になることもあるため、これを考慮しないと**開閉器が誤作動(トリップ)**してしまうことがあります。
📌 負荷の特性を理解しよう
電気設備で扱う負荷には主に以下の2種類があります:
| 負荷の種類 | 主な例 | 特徴 |
|---|---|---|
| 動力負荷 | モーター、電熱器、空調機など | 始動電流が大きい、連続運転あり |
| 電灯負荷 | 照明、コンセント、事務機器など | 比較的安定した消費電流、突入電流は少ない |

🔥 電熱器はどう考える?
電熱器(ヒーターなど)は、始動電流が存在しないため、動力負荷であっても電灯負荷に近い扱いが可能です。
→ 始動電流を考慮せずに開閉器サイズを決めても問題ありません。
⚡ 開閉器サイズの選定で混同に注意!
-
電動機(モーター)系負荷
→ 始動電流を考慮し、定格電流より大きめの開閉器を選定する必要あり
(例:始動電流が定格の6倍になるケースも) -
電灯負荷/電熱器系負荷
→ 計算上始動電流は考慮しないものとし、実使用電流に応じて開閉器を選定
📌 これらを混同して同じサイズで設計してしまうと、誤動作や機器故障の原因になるため、必ず分けて考えましょう!
⚙️ 負荷の区分

| 負荷の種類 | 主な設備例 | 始動電流の考慮 | トリップの考え方 | 選定のポイント |
|---|---|---|---|---|
| 電動機(モーター) | 換気扇、ポンプ、コンプレッサー等 | 必要(大) | 定格電流+始動余裕 | 始動電流に耐えるよう大きめの開閉器を選ぶ |
| 空冷ヒートポンプ | パッケージエアコン等 | 必要(中) | 過負荷トリップさせない | 高温・低温運転で負荷変動に耐えるよう選定 |
| 電熱器 | 温水器、ヒーター等 | 不要 | 定格電流を基準 | 実使用電流に対して適正サイズでOK |
| 電灯 | 照明、コンセント、OA機器など | 不要 | 定格電流を基準 | 合計電流値に20〜30%程度の余裕で選定 |
電動機(モーター)回路のブレーカー選定ルール
📘どういう内容?
電動機(モーター)を動かすための回路には、「過電流遮断器(ブレーカー)」をつけます。でも、モーターって電源を入れた瞬間に**ドーン!と大きな電流(始動電流)**が流れるんです。そこで、ブレーカーを選ぶときは以下のようなルールがあります。
✅わかりやすく整理!
① 定格電流の上限ルール
| 電動機の定格電流 | ブレーカー定格電流の上限 |
|---|---|
| 50A以下 | 電動機定格電流の 3倍 + 他の機器の電流合計以下 |
| 50A超 | 電動機定格電流の 2.75倍 + 他の機器の電流合計以下 |
-
※「他の機器」…同じ分岐回路に繋がっている電熱器などがあれば、その分も足す必要あり
② 始動電流ですぐに切れちゃダメ!
-
モーターを始動するときに流れる大電流で、ブレーカーが誤作動しないようにすること!
③ 保護協調がOKなら特例あり
-
モーターに**過負荷保護装置(サーマルリレーなど)**があって、ちゃんと役割分担できているなら…
➡️ 電線の許容電流の2.5倍までブレーカーを大きくしてもOK!
✅ 過電流遮断器の選定ルール【解釈149】
① 遮断器の定格電流(基本ルール)
以下の条件をすべて満たす範囲内で選定します:
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 上限値1 | 電動機の定格電流 × 3(50A超は2.75)+ 他の機器の定格電流合計 |
| 上限値2(特例) | 電線の許容電流 × 2.5 以下であればOK(※保護協調が取れていれば) |
| 始動電流への配慮 | モーターの始動電流ではトリップしない定格を選ぶ |
📌「始動時にトリップしないように」が特に重要です。
🎓かんたんに言うと?
🔍ポイント
-
ブレーカーはモーター定格電流の3倍以内(または2.75倍以内)
-
他の機器の電流も合算して考える
-
始動電流で誤作動しないブレーカーにする
-
過負荷保護装置がある場合は、電線の許容電流の2.5倍までOK
開閉器を求める基本的な手順


- 電動機の開閉器サイズは負荷電流によって求めるだけではありません。
- もともとの電流値より係数を見込んで選定するため負荷電流より大きいサイズが選定されます。
📝 まとめ
動力負荷のブレーカーサイズの選定方法
3.電動機に電気を供給する分岐回路の過電流遮断器の選定は,次の各号による
こと。(解釈149)
① 過電流遮断器の定格電流は,
当該電動機の定格電流の3倍(電動機の定格電流が50Aを超える場合は,2.75倍)に他の電気使用機械器具の定格電流の合計を加えた値以下
で,かつ,電動機の始動電流により動作しない定格のものであること。ただし,電動機の過負荷保護装置との保護協調が適切であるときは,
当該分岐回路に使用する電線の許容電流の2.5倍以下とすることができる。


負荷電流の3倍よりケーブルの許容電流の方が小さい場合
負荷に電動機を含む場合
| 電動機あり | 2.5IW < 3IM + IH | IB ≦ 2.5IW |
ケーブルの許容電流×2.5<電動機の定格電流×3+その他の負荷の定格電流のとき
過電流遮断器≦ケーブルの許容電流×2.5を選定します
| 項目 | 要点 |
|---|---|
| 開閉器の定格 | 遮断器以上の定格電流で選定 |
| 遮断器の選定 | 「定格電流×3」+他機器電流、始動電流を考慮 |
| 電線100A超の特例 | 標準定格がなければ「直近上位定格」でOK |
| 特例構成(複合保護) | 遮断器定格は電線許容電流以下でも可(要保護協調) |
| 保護協調 | サーマル・遮断器間の動作バランスがとれているか確認が必須 |