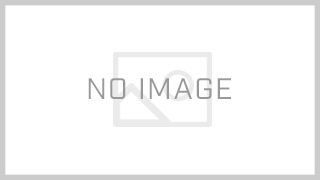レースウェイの耐震支持とは?―設置例と注意点を図解で解説!
地震対策として注目される電気設備の耐震支持。今回は「レースウェイ(金属線ぴ)」の耐震支持について、どのような場合に必要なのか、具体的な施工例や注意点をわかりやすく紹介します。
✅ レースウェイは基本的に「耐震支持不要」?
レースウェイは金属製の細い配線ルートで、周長が80cm以下のものについては、「建築センター指針」において耐震支持の適用除外とされています
ただし──
📌 設計図書で「耐震支持を行うこと」と明記されている場合は、基本として施工が必要です。
「周長が80cm以下」とは、電気設備において配線や配管などの外周の長さが80cmを超えないものを指します。
🔎 周長とは?
周長(しゅうちょう)は、「物体の外枠をぐるっと一周したときの長さ」のことです。
たとえば、以下のように計算されます:
【例1】丸い金属管(円形断面)
-
直径が約25.5cmの場合
-
周長 = 直径 × π(約3.14)
-
周長 ≒ 25.5cm × 3.14 ≒ 80cm

【例2】長方形のダクト
-
幅30cm × 高さ10cm の場合
-
周長 = (30 + 10) × 2 = 80cm

✅ なぜ「周長80cm以下」が基準なのか?
これは建築センター指針などで耐震支持の適用除外基準として定められており、「構造的に軽量で、地震時に落下や損傷のリスクが比較的少ない」とされているためです。
そのため、φ82mm以下の単独管や、外周80cm以下のダクト・レースウェイなどは原則として耐震支持が不要とされます。
🛠 レースウェイの耐震支持例【図解】
以下の図は、「建築センター指針」第3.1.9図に基づいた施工例です。
📷 図(a):側面から見たレースウェイの固定例(イメージ)

壁などの構造物に固定します
📷 図(b):断面から見たレースウェイの固定例(イメージ)

吊り金物に対し振れ止めで固定します
🔧 設計・施工時のポイントまとめ
-
✅ 支持間隔は12m以内とし、現場の状況に合わせて配置します。
-
✅ ブレース材(筋かい)を必ず設置。固定は「ボルト固定式」または「ワイヤー式」どちらでも可。
-
✅ ブレース材には常にテンションがかからないようにする。
-
✅ 横方向と軸方向(配線の方向)の両方の揺れに対応するように設計する。
💡 まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基本的な扱い | 周長80cm以下 → 耐震支持は「原則不要」 |
| 例外 | 設計図に「耐震支持あり」と明記されている場合は必要 |
| 支持間隔の目安 | 12m以内 |
| 使用する部材 | ブレース材(ボルト式またはワイヤー式)、振れ止め、吊金物など |
| 注意点 | 常時テンションをかけず、横揺れ・縦揺れ両方に対応する構成とすること |