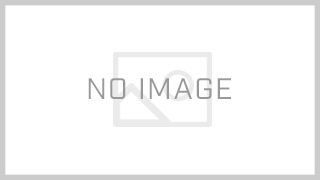スポンサーリンク
contents
スポンサーリンク
✅ 質問の概要:
高圧受電設備には**容量制限(例:300kVA以下)**がありますが、
その根拠や考え方は?どの法令・規格に基づくの?
✅ 答えのポイント
-
容量制限は、安全性・保守性・周囲環境への影響配慮のために設けられている
-
該当する規定は:
▶︎ 高圧受電設備規程 1110-5条「受電設備容量の制限」
🔍 解説:受電設備容量の考え方
-
受電容量=受電電圧で使用する変圧器、電動機、機器の合計容量(kVA)
-
高圧電動機は「定格出力(kW)」ではなく「kVA」で算定
-
高圧進相コンデンサは、JIS C 4620 の定義により容量に含めない
🔢 規定の上限「300kVA」の理由は?
PF・SF形キュービクル式高圧受電設備については:
| 内容 | 詳細 |
|---|---|
| 容量制限の対象 | 箱型・屋外式を除く、屋内設置のPF・SF型キュービクル |
| 制限容量 | 300kVA以下と規定 |
| 根拠 | 配電変電所のOCR(過電流継電器)とPF・SFの限流ヒューズとの動作協調 |
📌 なぜ動作協調が重要?
もしOCRとヒューズの協調がとれていないと…
停電リスク
設備破損
感電・火災の危険
→ だから、制限内で安全性を担保することが求められる!
⚡PF・SF形受電設備の容量制限(300kVA)と動作協調の考え方
🧠 解説:なぜPF・SFは300kVA制限なの?
1. 屋外式で箱に収める構造のPF・SFは、
-
保守性や環境耐性に制約あり
-
そのため、設備容量は最大300kVAまでとされている(※他方式は上限なしもある)
2. 制限の根拠は「動作協調」にあり!
-
高圧規程「動作協調1」では:
「PF・SF形の主遮断装置と配電変電所のOCRとの協調」が求められる
⚙ 設定条件の具体例(本文より)
-
配変OCR:200/5A、タップ6A、タイムレバー #1
-
→ このOCR特性と限流ヒューズの遮断特性がぶつからないように設定
-
自家用PFでも、OCR設定に応じて限流ヒューズを選定する必要あり
✅ キーワード解説
| 用語 | 解説 |
|---|---|
| PF・S形 | パッケージ型(箱入り)の屋外高圧受電装置 |
| OCR | 過電流継電器。電流が異常時に遮断信号を出す機器 |
| 動作協調 | ヒューズ・継電器などが順番に正しく作動するように調整すること |
| 限流ヒューズ | 大電流を短時間で遮断するヒューズ(開閉器内に内蔵) |
✅ まとめ:なぜ300kVAなのか?
| 理由 | 内容 |
|---|---|
| 保守・耐環境性の限界 | 箱入り構造ゆえに大容量化には不向き |
| 配電変電所との協調 | OCRと限流ヒューズのタイミングがズレると事故に直結 |
| 高圧規程の明確な指針に基づく | 「動作協調1」にて数値と条件が規定されている |
主遮断装置の形式と受電設備方式による設備容量の上限
(高圧規程1110-1表)
| 受電設備方式 | 主遮断装置の形式 | CB形(kVA) | PF・S形(kVA) |
|---|---|---|---|
| 箱に収めないもの(屋外式) | 屋上式 | 制限なし | 150 |
| 箱に収めないもの(屋外式) | 柱上式 | – | 100 |
| 箱に収めないもの(屋外式) | 地上式 | 制限なし | 150 |
| 箱に収めないもの(屋内式) | 制限なし | 300 | |
| 箱に収めるもの(屋内式) | キュービクル | 4,000 | 300 |
| 箱に収めるもの(屋内式) | その他 | 制限なし | 300 |
✅ ポイント:
-
**CB形(遮断器)**は基本的に容量制限なし
-
PF・SF形は構造的制約から容量制限あり
-
屋外柱上式では最大100kVA
-
屋内で箱収めなら最大300kVA
-
【表2】限流ヒューズの最大適用の例(定格電流ごとの制限)
| 項目 | ||
|---|---|---|
| 定格電流(A) | G50 (G40) | G75 (G50) |
| 受電電力(kW) | 150 | 195 |
| 三相変圧器容量(kVA) | 150 | 200 |
| 単相変圧器容量(kVA) | 75 | 100 |
| 合計変圧器容量(kVA) | 225 | 300 |
| OCR設定(例) | CT比200/5A・タップ6A・TL#1 | CT比400/5A・タップ4A・TL#1 |
| OCR整定(静止) | 240A相当(一次) | 320A相当(一次) |
✅ 限流ヒューズの選定条件:
-
電力会社側の配電用OCRとの協調が前提
-
例)G50(150A)は最大225kVA程度まで、G75(195A)は最大300kVAまでが安全範囲
✅ まとめ:実務上の注意点
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| PF・SF形は300kVAまで | 箱収め設備(屋内)でも容量制限あり |
| 柱上式ではもっと小さい | 100kVAが上限(保守性や安全性の観点) |
| ヒューズ容量も制限要素 | G50=225kVA、G75=300kVAが上限目安 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク