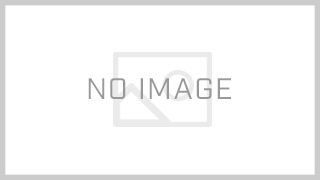出典(内線規程(JEAC8001-2022))より
- 記事のテーマ
- ケーブルとは?
- 施設方法のルール
- 埋め込みのルール
- 保護と埋設のルール
- ケーブルの支持方法のルール
- 支持点間の距離とは?
- ケーブル支持点間の距離ルール
- ケーブルの施設方法と支持点間距離のルールSS
- 垂直ケーブルの施設ルール
- 垂直ちょう架用線付きケーブルの施設ルール
- 鉄線がい装ケーブルの施設ルール
- ケーブルの屈曲ルール
- ケーブル屈曲の重要性
- 単心より合わせの場合
- 分割圧縮より線の場合
- ケーブルの接続ルール
- ケーブルと器具端子の接続ルール
- ケーブルとがいし引き配線の接続ルール
- ジョイントボックスと接続器具の点検ルール
- 大断面積ケーブル接続時の保護ルール
- ケーブルと絶縁電線の接続ルール
- ケーブル管内施設の電磁的平衡ルール
- 300V以下のケーブル配管等の接地ルール
- 300Vを超えるケーブル配管等の接地ルール
記事のテーマ
電気設備の安全性を確保するための、ビニル外装ケーブル等の施設方法に関するルールについて解説する。
ケーブルとは?
ケーブルとは、ビニル外装ケーブル、クロロプレン外装ケーブル、ポリエチレン外装ケーブルの総称です。これらのケーブルは、屋内配線などに広く使用されています。
施設方法のルール
施設場所の制限
重量物の圧力又は著しい機械的衝撃を受けるおそれがある場所にケーブルを施設してはいけません。
ただし、その部分のケーブルを金属管、ガス鉄管、合成樹脂管などに収めるなど適当な防護措置を講じる場合は、この限りではありません。
防護管の内径は、ケーブルの仕上り外径の1.5倍以上必要です。
ただし、防護管が短小で屈曲がなく、ケーブルの引き替えが容易なものは、ケーブルの仕上り外径の1.5倍未満のものを使用してもよい。
屋側及び屋外における防護範囲は、少なくとも構内においては地表上1.5m、構外においては地表上2mの高さから下の部分とする必要があります。
ケーブルをコンクリートに直接埋め込む場合は、打設時に重量物の圧力又は著しい機械的衝撃を受けるおそれのある場所とみなされます。
埋め込みの制限
床、壁、天井、柱などに直接埋め込んではいけません。
ただし、次のいずれかにより施設する場合は、この限りではありません。
a. ケーブルを十分な太さの金属管、ガス鉄管、合成樹脂管などに収めて施設する場合
b. 短小な貫通箇所において適当な穴を通して施設する場合
穴は、ケーブルが損傷しない程度の大きさが必要です。
埋め込みのルール
木造家屋への埋め込み
木造家屋の真壁の埋込み、大壁の空洞部分、天井ふところその他これらに類する場所にケーブルを施設することができます。
ただし、くぎ打ちなどのおそれがあるときは、その部分のケーブルの前面には厚さ1.2mm以上の亜鉛メッキ鋼板又はこれと同等以上の強さ及び耐腐食力のある防護材を施設する必要があります。
特に大壁の空洞部分などにケーブルを施設する場合で、上記防護材を施設する場合以外は、柱、間柱等に沿わせてケーブルを固定しないのがよい。
コンクリート、れんが、ブロック、石材などへの埋め込み
技術上やむを得ない場合において、壁、門、へいなどを構成するコンクリート、れんが、ブロック、石材などの外面に溝を掘り、その中へ埋め込むか、又はブロック穴(空洞)の部分を通してケーブルを施設することができます。
この場合、ケーブルのボックス挿入部分には、ゴムブッシングなどを使用し、水分などの浸入を防止する必要があります。
耐火構造への埋め込み
耐火構造で既設分岐回路から延長する場合で、天井又はしっくい内にケーブルを埋め込むことができます。
この方法により施設すると容易にケーブルの引き替えができなくなるので、点滅器、コンセントなどの引下げ配線のように配線の末端に限るのがよい。
保護と埋設のルール
管の端口の保護
防護に使用する金属管、ガス鉄管、合成樹脂管などの管の端口は、なめらかにするなどケーブルの引き入れ又は引き替えなどの際に被覆を損傷しないようにする必要があります。
ボックス挿入時の保護
ケーブルを金属製のボックスなどへ挿入する場合は、ゴムブッシング、ケーブルコネクタなどを用いてケーブルの損傷を防止する必要があります。
構内埋設
ケーブルを需要場所の構内に埋設する場合は、2400-1(地中電線路の施設方式)及び2400-11(地中電線の露出部分の防護)の規定に準じ、直接埋設式又は管路式により施設する必要があります。
ただし、住宅の構内の門灯、庭園灯、物置などへ配線する場合であって、重量物の圧力を受けるおそれがない場所に施設するものは、電線の上部を堅ろうな板又はといで覆い損傷を受けるおそれがない場合に限り、土冠を30cm以上とすることができます。
ケーブルの支持方法のルール
支持材の選定と固定
ケーブルを施設する場合の支持は、当該ケーブルに適合するクリート、サドル又はステープルなどを使用し、かつ、ケーブルを損傷しないように堅ろうに固定して施設する必要があります。
屋側、屋外でのケーブルの支持にステープルを使用した場合は、造営材などの老朽化及び腐食などにより脱落するおそれがあるので、耐久性を有するサドル及びビスを使用する必要があります。
「ステープル」は、「ステップル」ともいわれています。
支持点間の距離
ケーブルを造営材の側面又は下面に沿って施設する場合の支持点間の距離は、2m以下とする必要があります。
支持点間の距離とは?
支持点間の距離とは、ケーブルを固定する支持材(クリート、サドル、ステープルなど)の間隔のことです。
ケーブル支持点間の距離ルール
| 施設の区分 | 支持点間の距離 (m) |
|---|---|
| 造営材の側面又は下面において水平方向に施設するもの | 1以下 |
| 接触防護措置を施してないもの | 1以下 |
| その他の場所 | 2以下 |
| ケーブル相互並びにケーブルとボックス及び器具との接続箇所 | 接続箇所から、0.3以下 |
ケーブルの施設方法と支持点間距離のルールSS
-
ころがし
- ケーブルは、隠ぺい配線の場合において、ケーブルに張力が加わらないように施設する場合に限り、ころがしとすることができます。
-
ラックなどへの施設
- ラックなどは、ケーブルの重量に十分耐える構造であって、かつ、堅固に施設する必要があります。
- ラックなどにケーブルを施設する場合のケーブルの支持点間の距離は、ケーブルが移動しない距離とする必要があります。
-
造営材に沿わない場合の支持点間距離
- ケーブルを造営材に沿わずに施設する場合の支持点間の距離は、次項に規定する場合を除き2m以下とする必要があります。
-
2mを超える支持方法
ケーブルを造営材に沿わずに施設する場合の支持点間の距離が2mを超える場合には、次の各号による必要があります。
造営材相互間に板など(たわみ難いものに限る。)を固定し、この板に固定するか、又はケーブルをメッセンジャーワイヤでちょう架する必要があります。
メッセンジャーワイヤにケーブルをちょう架して施設する場合は、径間を15m以下とし、かつ、次による必要があります。
a. メッセンジャーワイヤは、引張強さ2.36kN以上の金属線又は直径3.2mm以上の亜鉛めっき鉄線で、かつ、当該ケーブルの重量に十分耐えるものである必要があります。
b. 当該ケーブルには、張力が加わらないように施設する必要があります。
c. ちょう架は、当該ケーブルに適合するハンガー又はバインド線によりちょう架し、かつ、支持点間を50cm以下とする必要があります。
垂直ケーブルの施設ルール
- ケーブルの種類
垂直ケーブルに使用するケーブルは、以下のいずれかに適合する必要があります。
① ビニル外装ケーブル又はクロロプレン外装ケーブルであって、以下のいずれかに適合するもの
a. 導体が銅のものにあっては、公称断面積が22mm²以上のもの
b. 導体がアルミニウム(軟アルミ線、半硬アルミ線及びアルミ成形単線並びに鋼心アルミ導体を除く。)のものにあっては、公称断面積が30mm²以上のもの
c. 導体が鋼心アルミ導体のもの
- ちょう架用線
ちょう架用線は、引張強さが5.93kN以上の金属線又は断面積が22mm²以上の亜鉛めっき鉄より線である必要があります。
ちょう架用線の断面積は、5.3mm²以上である必要があります。
- ケーブルとの一体化
ちょう架用線は、当該ケーブルの外装と一体に堅ろうに取り付けられている必要があります。
- 引抜力
ちょう架用線は、当該ケーブルの自重(ちょう架用線の重量を含まない。)の4倍の引抜力に耐えるように取り付けられている必要があります。
- 座床
鉄線がい装ケーブルは、外装を損傷しないように座床を設ける必要があります。
- 鉄線
鉄線は、亜鉛メッキを施した鉄線であって、引張強さが294N以上のもの又は直径1.0mm以上の金属線を密により合わせたものである必要があります。
-
分岐線
- 分岐線は、ケーブルである必要があります。
- 分岐線の範囲は、垂直ケーブルから分岐して、配電盤、分電盤又は電気機械器具に至る部分の電線とします。
- 分岐線は、ケーブルである必要があります。
-
安全率
- 垂直ケーブル及びその支持部分の安全率は、4以上である必要があります。
- 安全率4を確保するためのつり下げ距離の計算方法は、資料3-1-2に示されています。
- 垂直ケーブル及びその支持部分の安全率は、4以上である必要があります。
-
張力と振留装置
- 垂直ケーブルは、張力が加わらないように施設し、かつ、分岐部分には、振留装置を施す必要があります。
-
追加の振留装置
- 上記の規定により施設してもなおケーブルに障害を及ぼすおそれがある場合は、さらに振留装置を施す必要があります。
-
導体の上部終端
- 導体の上部終端は、がいしその他堅ろうな絶縁物を用いてちょう架し、これを造営材等に堅ろうに取り付け、裸充電部分を当該ケーブルの線心の絶縁部分と同等以上の強さ及び絶縁効力のあるもので十分被覆する必要があります。
-
多心ケーブル
- 多心ケーブルにあっては、各導体に荷重が均等に加わるように施設する必要があります。
垂直ちょう架用線付きケーブルの施設ルール
-
ちょう架用線の支持
- ちょう架用線は、その支持点を造営材等に堅ろうに取り付ける必要があります。
-
ちょう架用線の補強
- ちょう架用線を支持するためにちょう架用線とケーブル本体とを分割する箇所は、ちょう架用線とケーブルとの離脱が下部に及ばないように補強する必要があります。
-
荷重の均等化
- 二以上のちょう架用線を有するケーブルにあっては、各ちょう架用線に均等に荷重が加わるように施設する必要があります。
鉄線がい装ケーブルの施設ルール
保持装置による把持と取り付け
鉄線がい装ケーブルを垂直ケーブルに使用する場合は、適切な保持装置を用いて把持し、これを造営材等に堅ろうに取り付ける必要があります。
使用制限場所
鉄線がい装ケーブルは、以下の場所に施設してはいけません。
3405節(粉じん危険場所)
3415節(ガス蒸気危険場所)
3420節(危険物などの存在する場所)
3425節(腐食性ガスなどのある場所)
3430節(火薬庫などの危険場所)
ケーブルの屈曲ルール
-
屈曲部の内側の半径
- ケーブルを曲げる場合は、被覆を損傷しないようにし、その屈曲部の内側の半径は、3165-2表による必要があります。
-
ビニル外装ケーブル(平形)の特例
- ただし、応接間、居間などのビニル外装ケーブル(平形)の露出配線でやむを得ない場合は、ケーブルの被覆にひび割れを生じない程度に屈曲させることができます。
3165-2表 ケーブル屈曲部の内側の半径
| ケーブルの種別 | 多心/単心より合わせ | 単心 |
|---|---|---|
| 遮へい無し | 仕上り外径の6倍以上 | 仕上り外径の8倍以上 |
| 遮へい有り(高圧含む) | 仕上り外径の8倍以上 | 仕上り外径の10倍以上 |
ケーブル屈曲の重要性
ケーブルを曲げる際には、被覆を損傷しないように注意する必要があります。被覆が損傷すると、漏電や短絡などの事故につながる可能性があります。
単心より合わせの場合
単心より合わせにおける仕上り外径は、より合わせ外径を指します。
分割圧縮より線の場合
単心であって、導体が分割圧縮より線の場合、仕上り外径の12倍以上とする必要があります。
分割圧縮より線とは、素線をより合わせて圧縮成形された分割部分導体(扇形)をより合わせて円形に成形された導体であり、主に導体サイズ800mm²以上に適用されます。
ケーブルの接続ルール
-
接続方法
- ケーブルを接続する場合は、1335-7(電線の接続)の規定によるほか、導体及び被覆物を損傷しないようにする必要があります。
-
ケーブル相互の接続
ケーブル相互の接続は、キャビネット、アウトレットボックス又はジョイントボックスなどの内部で行うか、又は適当な接続箱を使用して行い、接続部分を露出させない必要があります。
ただし、次の各号のいずれかによる場合はこの限りではありません。
① 接続部分及び被覆物が露出しないようにJIS C 2813 (1992)「屋内配線用差込形電線コネクタ」に適合する、ボックス不要形差込電線コネクタなどの接続器具を使用して施設する場合
ここでいう接続器具などによる接続例は資料3-1-3参照。
② やむを得ない場合で、ケーブルの絶縁体と同等以上の性能を有する合成樹脂によりモールドした場合又は絶縁チューブ等を使用して十分に被覆し、保護した場合
ここでいう絶縁チューブ等とは、接続部分のケーブルの被覆と一体化し、破壊しなければ取り外せないものをいいます。
ケーブルと器具端子の接続ルール
-
接続場所
- ケーブルを器具端子と接続する場合は、キャビネット、アウトレットボックスなどの内部で行う必要があります。
-
例外
- ただし、大壁、空どう部分、天井ふところ又はこれらに類する場所で、器具端子を堅ろうな難燃性絶縁物で密閉し、ケーブルの導体絶縁物を造営材より十分に離隔した場所にあっては、この限りではありません。
ケーブルとがいし引き配線の接続ルール
-
接続方法
- ケーブルとがいし引き配線を接続する場合は、外装をはぎ、心線をがいしで支持してIV電線相互の接続方法に準じて施工する必要があります。
-
ケーブル外装の終端
- この場合において、ケーブル外装の終端は、造営材から6mm以上離し、かつ、造営材に固定する必要があります。
-
ビニル外装ケーブルの接続例
- ビニル外装ケーブルの場合の接続例については、資料3-1-3を参照してください。
ジョイントボックスと接続器具の点検ルール
-
点検の必要性
- 端子金具を有するジョイントボックス及び接続器具などは、点検できるように施設する必要があります。
-
ねじ式端子金具の特例
- ただし、ねじ式の端子金具を有するジョイントボックスにあっては、ねじ部の緩み等を容易に点検できるよう露出場所に施設する必要があります。
大断面積ケーブル接続時の保護ルール
-
保護方法
- 断面積が大きいケーブル相互を接続する場合などであって、2項の規定(キャビネット、アウトレットボックス又はジョイントボックスなどの内部での接続)により難い場合は、黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープなどを使用して十分に被覆するか、又は絶縁用プラスチックチューブなどをはめることにより十分に保護する必要があります。
ケーブルと絶縁電線の接続ルール
-
接続方法
- ケーブルと絶縁電線を接続する場合は、絶縁電線相互の接続に準じて行う必要があります。
-
雨線外での接続
- 雨線外においては、ケーブル端を下方にわん曲して、被覆内に雨水が浸入しないようにする必要があります。
ケーブル管内施設の電磁的平衡ルール
-
磁性管の使用制限
- ケーブルを管の中に施設する場合に、同一管内を通る電流の電磁平衡がとれない場合は、管に磁性管を使用しない必要があります。
300V以下のケーブル配管等の接地ルール
-
接地工事の種類
- 使用電圧が300V以下の場合、ケーブルを収める管その他の防護装置の金属製部分、ラックなどの金属製部分及び金属製の電線接続箱などは、D種接地工事を施す必要があります。
-
接地省略の条件
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、接地を省略することができます。
① ラックなどの金属製部分又は防護装置の金属製部分の長さが4m以下のものを乾燥した場所に施設する場合
② 屋内配線の対地電圧が150V以下の場合において、ラックなどの金属製部分又は防護装置の金属製部分の長さが8m以下のものを乾燥した場所に施設するとき、又は簡易接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す設備と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施した場合
③ ラックなどの金属製部分が、合成樹脂などの絶縁物で被覆したものである場合
300Vを超えるケーブル配管等の接地ルール
-
接地工事の種類
- 使用電圧が300Vを超える場合、ケーブルを収める管その他の防護装置の金属製部分、ラックなどの金属製部分及び電線接続箱などは、C種接地工事を施す必要があります。
-
D種接地工事の適用
- ただし、接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す設備と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は、D種接地工事によることができます
まとめ
- ケーブルは、重量物の圧力や機械的衝撃を受ける場所に施設してはいけません。
- ただし、防護措置を講じる場合は、施設可能です。
- ケーブルをコンクリートに直接埋め込む場合は、防護措置が必要です。
- ケーブルは、床、壁、天井、柱などに直接埋め込んではいけません。
- ただし、管に収めるか、短小な貫通箇所に穴を通して施設する場合は可能です。
(注)
- この記事は、電気技術規程・解釈に基づいた一般的な情報提供を目的としています。
- 最新の情報については、関連法令をご確認ください。
(キーワード)
ビニル外装ケーブル、クロロプレン外装ケーブル、ポリエチレン外装ケーブル、ケーブル、施設方法、防護措置、コンクリート埋め込み、電線管、電気工事、電気技術規程、安全